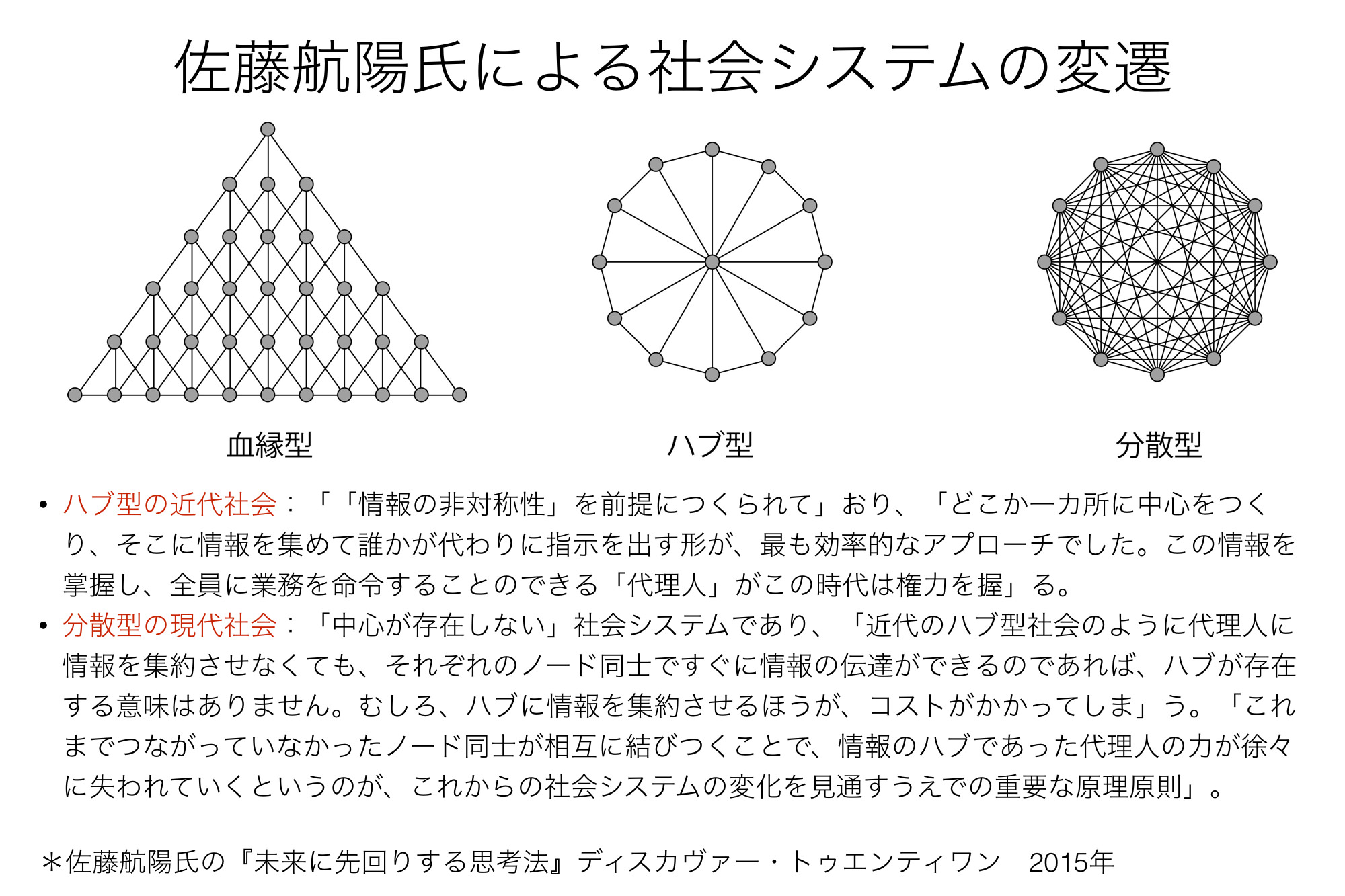調査でお世話になった居場所(まちの居場所)の運営者のご家族が亡くなられたという連絡がありました。居場所の運営において表に出てこられる場面は多くはありませんでしたが、背後からサポートし続けてこられた方です。
運営者ご自身も高齢であるため、子どもがその居場所を継ぐという話も出されているという話も伺いました。
各地に開かれている居場所の中にも、そこをどう継承していくかが切実な課題になっている居場所もあると思います。こうした切実な課題に対して、研究という行為はどう関わり得るのかということを考えます。
建築計画学で常に問われるのは、計画、つまり「これからどうするのか?」を考えること。ある事例(事例という表現はあまり好きではありませんが)の調査結果から、「これからどうするのか?」についての知見が求められるのは、建築計画学だけでないかも知れません。もちろんこれは非常に大切なこと。
ただし、忘れてはならないのは、建築計画学に限らず、研究にはある現象の記述、つまり、「これまでどうだったのか?」を捉えるという側面があること。アンケート調査であれ、観察調査であれ、インタビューであれ、文献調査であれ、全ての調査は記述という側面を持つ。「これからどうするのか?」が重視される場面では影に隠れてしまいがちですが、「これまでどうだったのか?」の記述自体が持つ価値を忘れてはならないと思います。
もしも、ある居場所が大切にされてきた価値をきちんと記述しておけば、たとえ「これからどうするのか?」についての知見には直接結びつかないとしても、居場所の継承という場面において、例えば、「親はこのようなことを大切にして居場所を運営してきたのか」などを知る場面において意味あるものになり得る。そして、長い目で見ればこのことが「これからどうするのか?」につながっていくのではないか。
こうした研究はもはや建築計画学とは呼ばないのかも知れませんが、調査結果から「これからどうするのか?」へと急ぐのではなく、調査結果の記述自体を大切にしておくというスタイル。それが結果として、「これからどうするのか?」につながる可能性にかけておくというスタイル。
既存の制度では上手く対応できないものに向き合うために同時多発的に開かれるようになった居場所に向き合うためには、こうしたスタイルが相応しいのかも知れません。