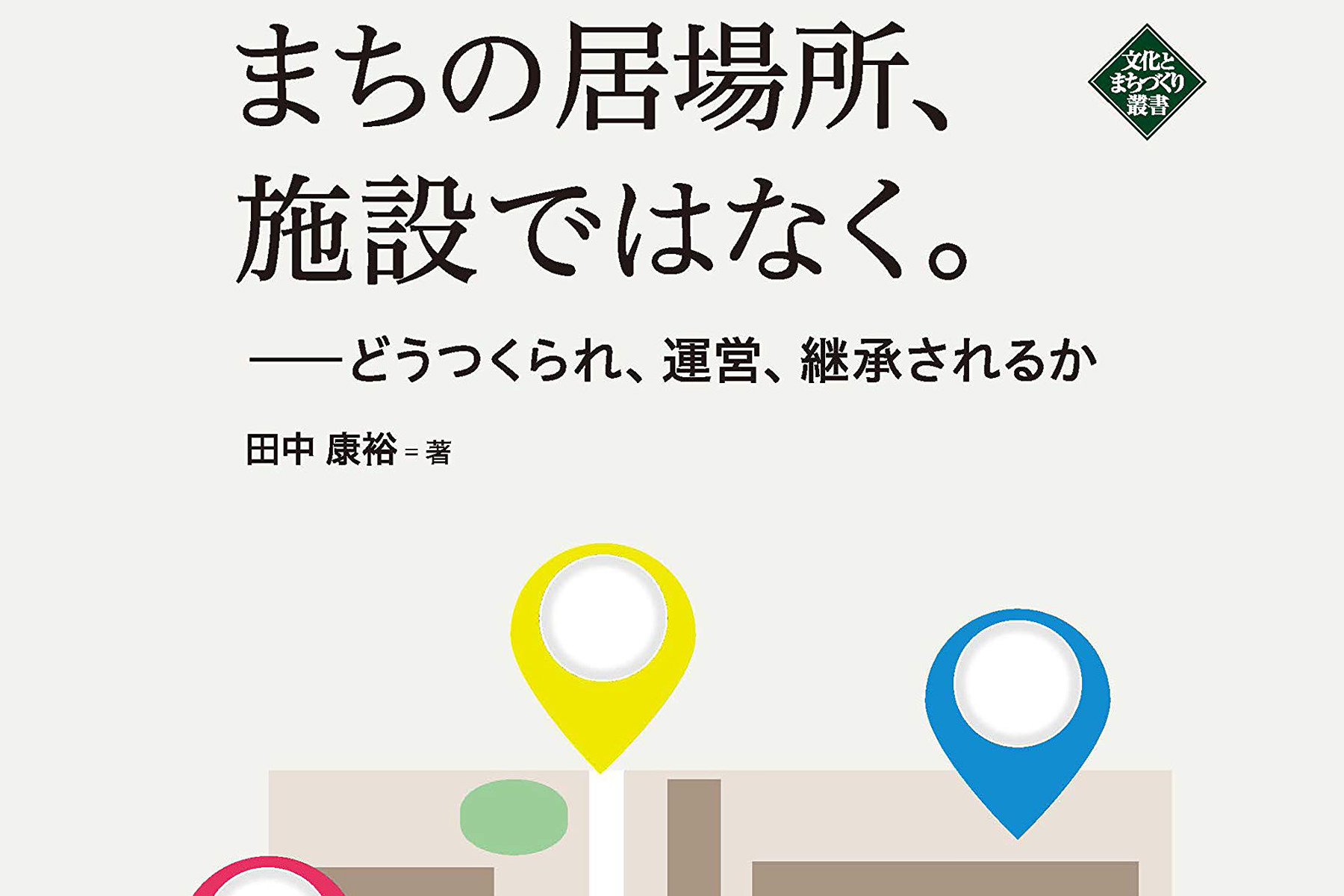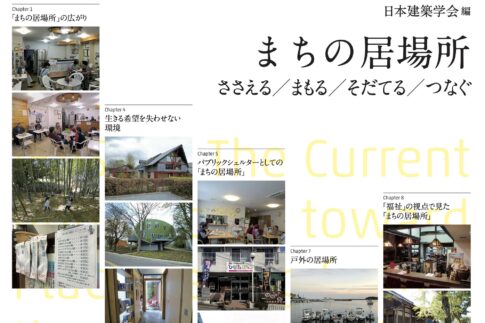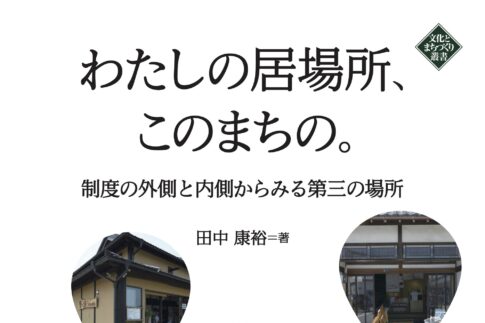豊中まちづくり研究所主催の第201回敬天塾で、「適度な距離をおいた他者との関係:居場所が実現する地域における助け合い」というテーマで、話題提供をさせていただくことになりましたのでご案内いたします。
適度な距離をおいた他者との関係:居場所が実現する地域における助け合い
第201回敬天塾
- 主催:豊中まちづくり研究所
- 日時:2025年11月18日(火)18時30分から
- 会場:阪急豊中駅前 ホテルアイボリー 2階 菫(すみれ)の間
- 会費:1,000円
- テーマ:適度な距離をおいた他者との関係:居場所が実現する地域における助け合い
- 講師:田中康裕(合同会社Ibasho Japan代表、千里ニュータウン研究・情報センター事務局長)
講演概要
今、さまざまな場面で地域における助け合いの必要性が言われています。地域における助け合いは自発的に行われるべきものですが、厚生労働省が「地域包括ケアシステム(※)」において「互助」を重要なものとして位置づけるなど、制度に期待されるものにもなっています。
地域における助け合いはどのようにすれば実現できるのか。助け合いを妨げるものとして、地域に助けを求めることのできる友人、知り合いがいないという「関係の希薄さ」がしばしばあげられます。しかし、「関係の希薄さ」以外にも、地域における助け合いを妨げてしまうものがあります。同じ地域の人「だからこそ」自分が弱った姿を見られたくはない、片付いていない家の中を見られたくはないという心理もまた、地域の人に助けを求めることを躊躇させる大きな理由になっています。それゆえ、地域における助け合いのためには、プライバシーを互いに侵さないという適度な距離をおいた関係が必要。新潟市の「実家の茶の間・紫竹」では、このような関係が、「矩(のり)を越えない距離感」と表現されています。
今回の敬天塾では、「実家の茶の間・紫竹」において、「矩(のり)を越えない距離感」を実現するためにどのような配慮がなされているかを紹介して、地域における助け合いのあり方について考えたいと思います。
(※)厚生労働省の「地域包括ケアシステム」のページでは、次のように説明されている。
「厚生労働省においては、2025年(令和7年)を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築を推進しています。」
講師プロフィール
2007年、大阪大学大学院工学研究科・博士後期課程修了、博士(工学)。大阪大学大学院工学研究科・特任研究員(2007〜2008年)、清水建設技術研究所・研究員(2008年~2013年)を経て、2013年から岩手県大船渡市の「居場所ハウス」の運営・研究に参加。2023年から合同会社Ibasho Japan代表。大阪大学在籍時から大阪府の千里ニュータウンの活動に参加しており、2012年から千里ニュータウン研究・情報センター(ディスカバー千里)の事務局長。
〈著書・共著〉田中康裕『わたしの居場所、このまちの。:制度の外側と内側から見る第三の場所』(水曜社, 2021年)、田中康裕『まちの居場所、施設ではなく。:どうつくられ、運営、継承されるか』(水曜社, 2019年)、日本建築学会編『まちの居場所:ささえる/まもる/そだてる/つなぐ』(鹿島出版会, 2019年)、ダチケンゼミ編『足立孝先生生誕百周年記念論文集:人間・環境系からみる建築計画研究』(デザインエッグ社, 2019年)、高橋鷹志・長澤泰・西村伸也編『環境とデザイン(シリーズ〈人間と建築〉3)』(朝倉書店, 2008年)など。
参加申し込み
敬天塾への参加は、こちらのページからお申し込みください。