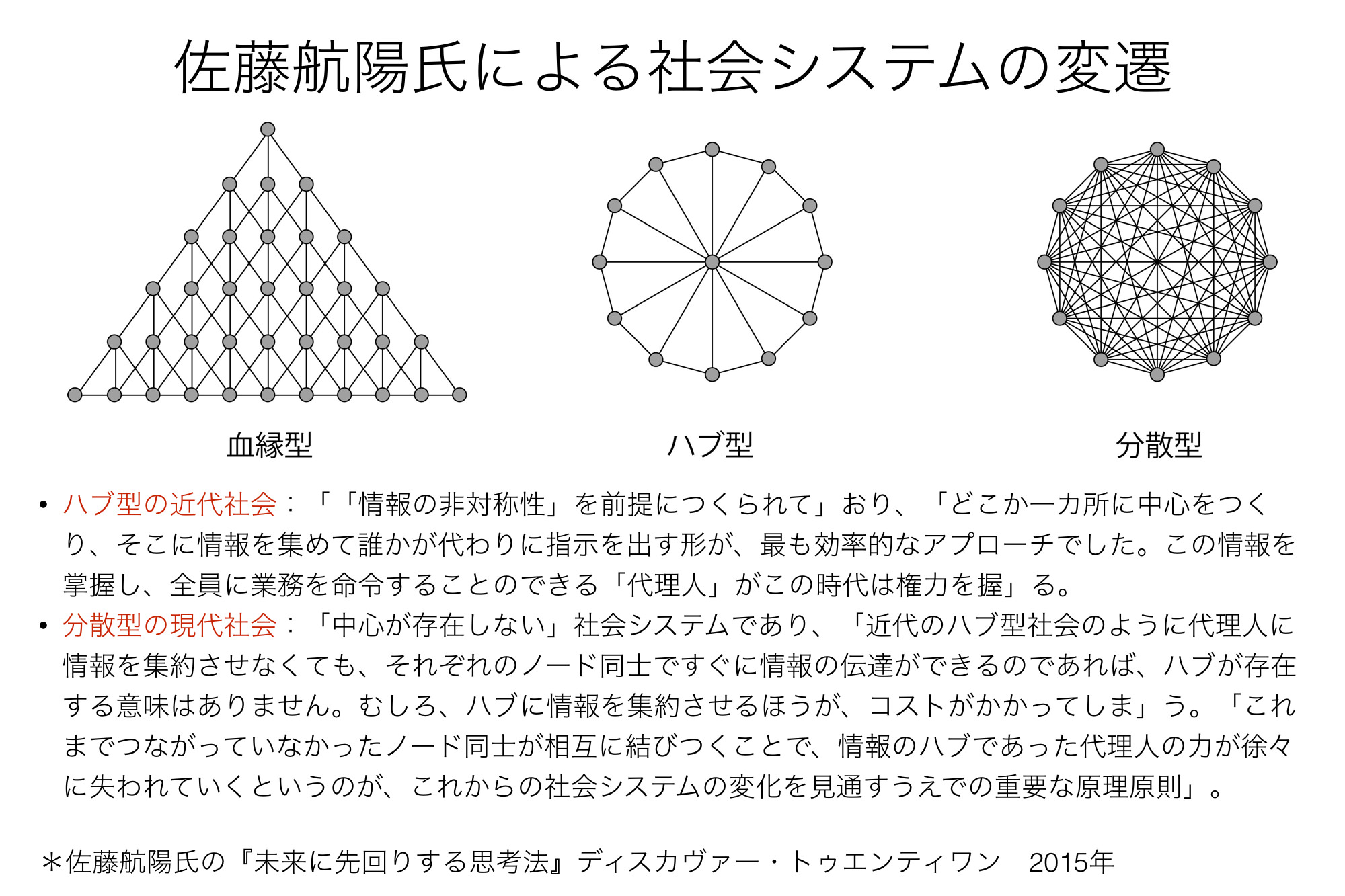2000年頃から各地に「まちの居場所」(コミュニティ・カフェ、まちの縁側、ふれあいの居場所など)が同時多発的に開かれるようになってきました。「まちの居場所」は不登校、遊び場の不足、育児をする親の孤立、虐待、貧困、退職後の地域での暮らし、介護、都市の空洞化、商店街の空シャッター街化、地方の人口減少などの切実な、けれども従来の施設・制度の枠組みでは十分に対応できない課題に対して、地域の人々自らが向き合い、乗り越えようとする中から生まれてきた場所だと捉えることができます。
「まちの居場所」はこのような草の根の動きとして、従来の施設ではない場所として生まれてきましたが、建築計画学で議論されるのは「まちの居場所」もまた新たなタイプの施設ではないか? ということです。
最近、広井良典『ポスト資本主義:科学・人間・社会の未来』(岩波新書 2015年)を読みました。広井氏はこの書において、科学((西欧)近代科学)は「(1)「法則」の追求 背景としての「自然支配」ないし「人間と自然の切断」」、「(2)帰納的な合理性(ないし要素還元主義) 背景としての「共同体からの個人の独立」」の2つの基本的な特質をもつと述べ、「前者は自然がそれに従って動くところの「法則(law)」を明らかにし、それを通じて自然をコントロールするという志向であり、後者は様々な事象を中立的・第三者的な観点から実証的ないし帰納的に把握し、かつそれらを個々の要素の集合体として理解するという志向を指している」と述べています。
これに対して、広井氏は、科学の新たな方向性について次のように述べています。
しかしながら現在求められているのは、自然科学に象徴される近代科学的なアプローチと、いわば「民俗学的・歴史学的アプローチ」とも呼びうるような、歴史性や風土、宗教や自然信仰、文化やコミュニティ等に着目したアプローチの両者を大きな視野で統合していくような、新たな「科学」ないし知のあり方ではないだろうか。
ところで、従来の科学の枠を超えるこうした新たな方向は、別の側面から見れば、普遍的な法則のみならず、特定の場所や空間の個別性や多様性に関心を向けた「ローカル」な科学あるいは知という性格を同時にもつことになるだろう。この場合、個別性や多様性に関心を向けるといっても、それは単にそれぞれの場所や対象の特徴を網羅的に記述するというだけにとどまるのではない。むしろ、なぜそのような個別性や多様性が生まれたかという、その背景までを含めた全体的な構造を把握し理解するというのが、ここでの「ローカルな科学/多様性の科学」の趣旨だ。
*広井良典『ポスト資本主義:科学・人間・社会の未来』岩波新書 2015年
広井氏のこの書を読み、「まちの居場所」が施設であるか否かは、「まちの居場所」をどのようなものとして捉えるかという視線によるのではないかと思いました。
日本では既に多くの「まちの居場所」が開かれていますが、これからますます「まちの居場所」は必要とされており、「まちの居場所」を開きたいと考えている人・組織は多いと思います。そして、行政もこうした動きに注目している。
「まちの居場所」で蓄積されてきたものを他へと伝えるために、「まちの居場所」を成立させるための条件を見出そうとする研究も行われると思います。この時、「まちの居場所」が施設化していくか否かは、「まちの居場所」をどのようなものとして捉えるかにかかっているのではないか。
施設というのは、学校(教育施設)、公民館(社会教育施設)、病院(医療施設)など、その名前を聞けばどんな場所かを思い描くできる建物で、制度的な裏付けがあって存在しているもの。建築計画学を例にとれば、研究者はこれらの建物のフィールドワークを重ねることで、規模、部屋のサイズ、各部屋の配置、動線などより良い学校を成立させるための条件を見出してきた。このようにして見出された条件は「歴史性や風土、宗教や自然信仰、文化やコミュニティ等」に関わらずに成立するものとして取り扱われたし、研究者自身も普遍性を過度に追求してきたという側面もあると思います。こうして全国一律の施設が普及してきたわけですが、このことは日本が近代化する上で大きく寄与したことは否定できない事実です。
学校とは異なり、「まちの居場所」はまだ現時点では施設にはなっていません。けれども研究者が様々な施設に対して行ったことを繰り返せば、即ち「歴史性や風土、宗教や自然信仰、文化やコミュニティ等」に関わらない「まちの居場所」を成立させる普遍的な条件を見つけ出そうとするならば、それは制度として使いやすいものであるがゆえに、「まちの居場所」は施設化してしまうのではないかと考えています。
もちろん施設が悪いというわけではありませんが、従来の施設・制度の枠組みでは十分に対応できなかった課題に向き合おうとする中から生み出されてきたのが「まちの居場所」だとすれば、施設化した「まちの居場所」からは漏れ落ちてしまう価値は多いのではないかと思います。
「まちの居場所」が本来持っていた可能性、価値を最大限にくみ取り、共有していくことが研究者の役割だとすれば。研究者が「まちの居場所」をどのようなものとして扱うのかという眼差しを再考する必要があるのではないか?
それは広井が指摘するように、「まちの居場所」を安易に一般化して語るのでもなく、逆に、個別を「網羅的に記述する」だけにとどまるのでもなく、「なぜそのような個別性や多様性が生まれたかという、その背景までを含めた全体的な構造を把握し理解する」という姿勢が求められるのだと思います。