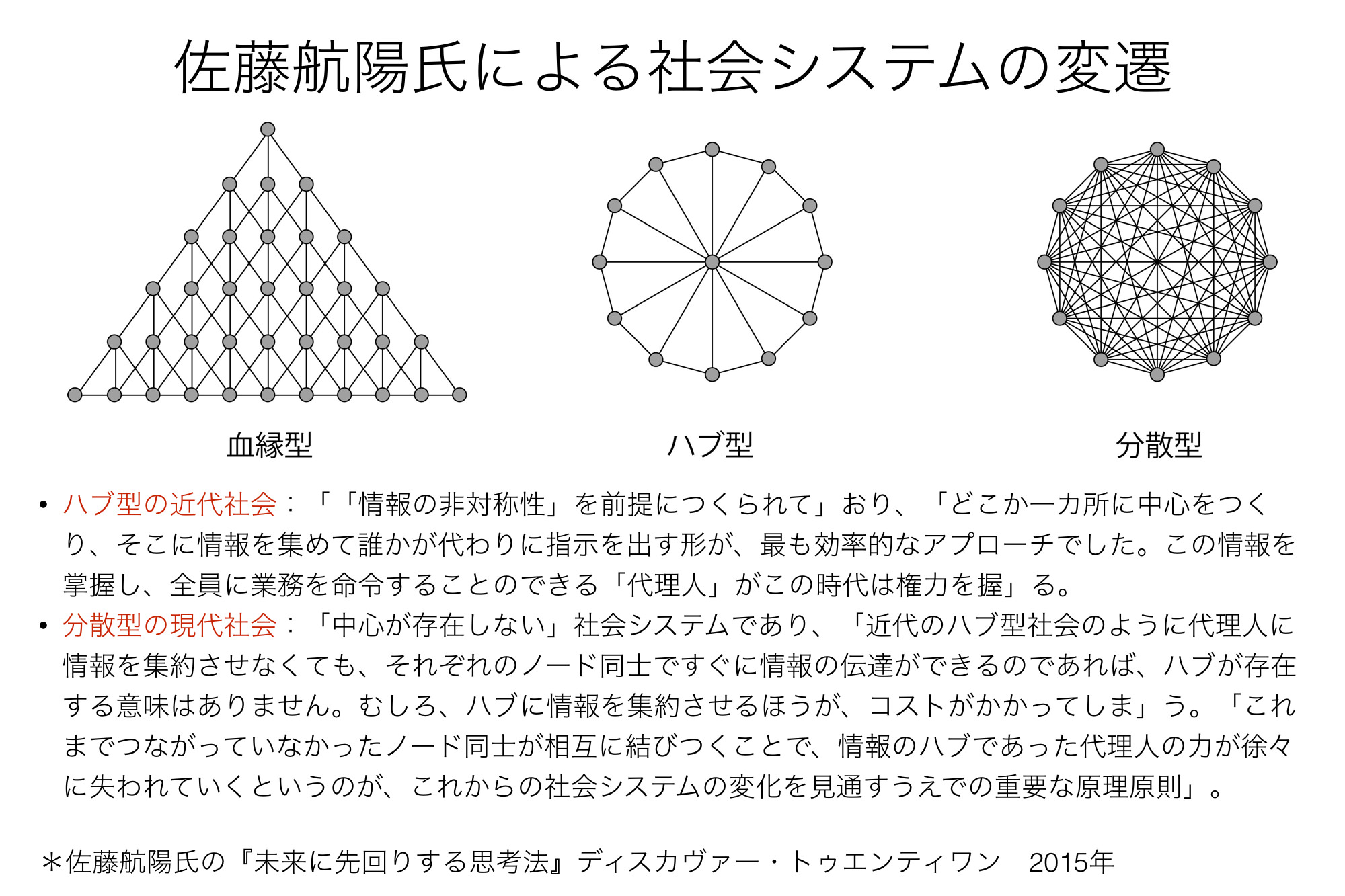山本義隆『近代日本一五〇年——科学技術総力戦体制の破綻』(岩波新書 2018年)を読みました。
この本で山本氏は「日本は、明治期も戦前も戦後も、列強主義・大国主義ナショナリズムに突き動かされて、エネルギー革命と科学技術の進歩に支えられた経済成長を追求してきたのであり、その意味では一貫している」とし、大学、(理科系の)研究者もその構成要素であると。現在の科研費(科学研究費助成事業)も、第二次世界大戦の戦時下において創設されたものであることも指摘されています。
研究のあり方について、山本氏は次のように指摘。科学的、合理的であることがすぐに民主的であることに結びつくことはなく、それは政治の問題であると。そして、(日本の公害の歴史において)「専門の知」は権力の側のものであったと。
「すくなくとも理科系の学問では、多くの学者は、おのれ自身の知的関心に突き動かされ、あるいは自身の業績をあげることを目的に、研究している。他方で、国家が科学と技術の研究を支援しているのは、それが、経済の発展、軍事力の強化、そして国際社会における国家のステータスの向上に資するがゆえに、である。そのことが民主主義の発展に結びつくかどうかは、まったく別の問題、つまり政治の問題である。にもかかわらず当時、科学的合理性と非科学的蒙昧の対比が民主制と封建制の対比として語られることによって、科学的は民主的とほとんど等置され、科学立国は民主化の軸と見なされた。」
「合理的」であること、「科学的」であることが、それ自体で非人間的な抑圧の道具ともなりうるのであり、そのことの反省をぬきに、ふたたび「科学振興」を言っても、いずれ足元をすくわれるであろう。それを私たちは、やがて戦後の原子力開発に見ることになる。」
「明治以来、国策大学として創られた帝国大学の学問は、多くの場合「専門家」の発する「科学的見解」として権威づけられることで、国家と大企業に奉仕してきたのである。日本の公害の歴史は「専門家」と「専門の知」が企業や行政、総じて権力の側のものであったことを示している。」
*山本義隆『近代日本一五〇年——科学技術総力戦体制の破綻』岩波新書 2018年
大学、あるいは、研究者はしばしば社会から遊離したものと見なされることがありますが、山本氏の指摘する通り社会のあり方に埋め込まれたもの。その時々でどのような研究テーマに注目が集まっているか(どのような研究テーマであれば研究資金を獲得しやすいか)というレベルでも、研究者自身がどのようなテーマに関心を持つようになったかというレベルでも。そうであるにも関わらず、社会から遊離したものと見なされるのは、誤認に過ぎない。
そうすると、「研究は社会の役に立たない」という研究者による表明は、この問題から逃げた無責任なものということになるのかもしれません。
研究が社会に埋め込まれたものであることから逃れられないのだとすれば、そのことを意識した上で、その研究が社会においてどのような意味をもつのか、どのような影響を与え得るのか、さらに、自身の研究はどのような社会のあり方を描こうとするのかという視野を持つことが、研究者それぞれが持つことが求められるのだと思います。