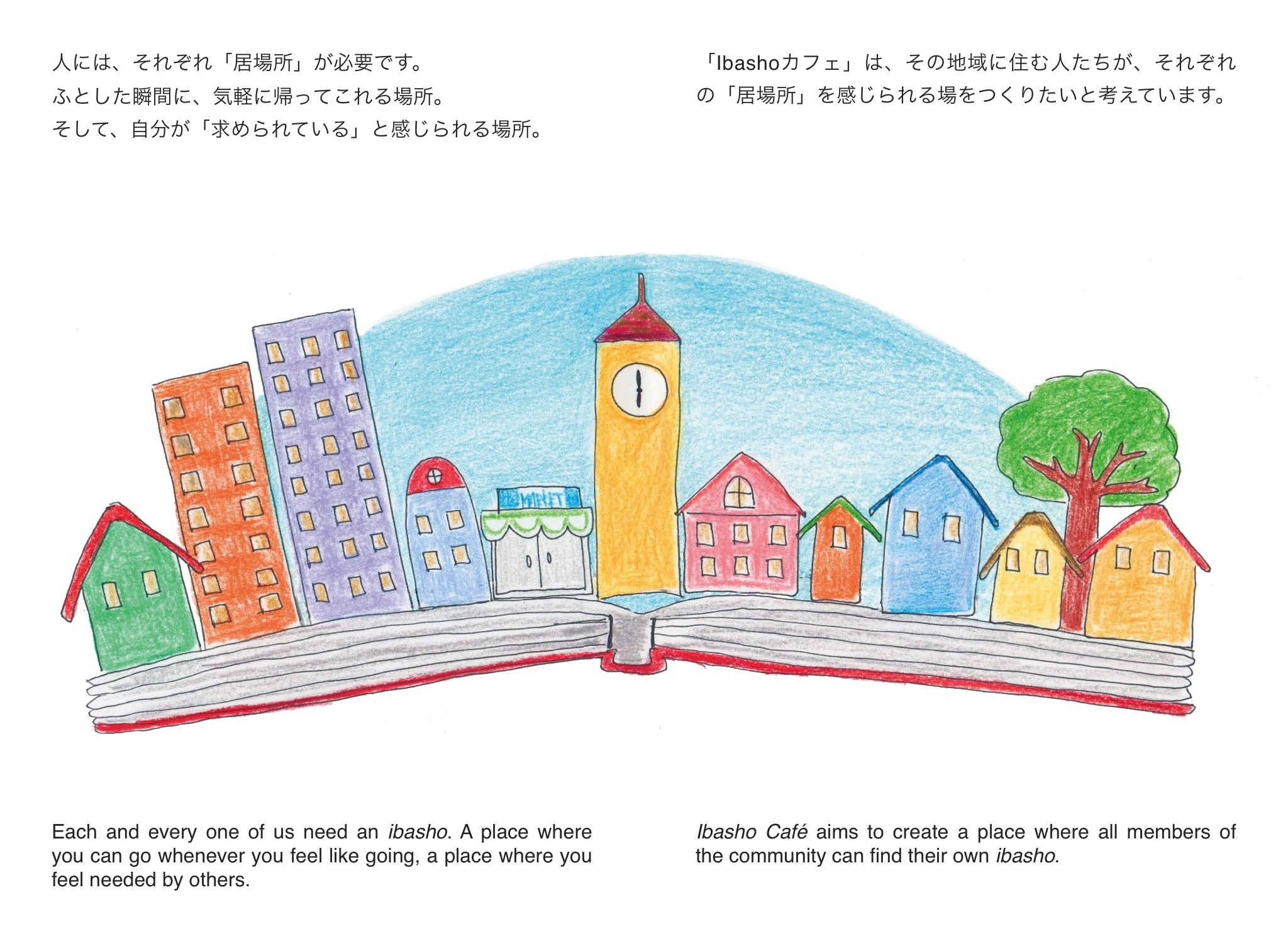2016年4月16日(土)に開催した高台移転した方/される方をまじえた交流歓迎会から、「居場所ハウス」では熊本地震の義援金を集めるための募金箱を設置し、多くの方に募金をしていただきました。
最初はペットボトルを活用した急ごしらえの募金箱でしたが、その後、メンバーの1人が手作りの募金箱を作ってくださいました。また、「居場所ハウス」で5月3日(火)に開催予定の鯉のぼり祭りではフリーマーケットを開催し、売上げを義援金にしようという提案もあります。
こうした動きが生まれているのは、「居場所ハウス」の設立を提案したワシントンDCの「Ibasho」代表のKさんの実家が熊本であり、また、デジタル公民館まっさきのメンバーが熊本に赴任したというように、顔の見える関係が築かれているというのが大きいと感じます。「お世話になったんだから、これぐらいのことはしないといけない」というのは、あるメンバーの話。
誰かに面倒をみられる存在、一方的にお世話される存在だと見なされる傾向にある高齢者が、自分たちにできる役割を担える場所であること。これは「Ibasho」が掲げる最も重要な理念ですが、上にあげたような動きにはまさにこの理念が現れていると感じます。
誰もが自分にできる役割を担えるという意味で、一人ひとりの高齢者は、個々の悩み事を抱えていたり、身体が思うように動かなかったりしたとしても、かけがえのない存在です。
少し話は逸れますが、最近、地域包括ケアシステムの構築が進められています。厚生労働省のウェブサイトには次のような説明があります。
日本は、諸外国に例をみないスピードで高齢化が進行しています。
65歳以上の人口は、現在3,000万人を超えており(国民の約4人に1人)、2042年の約3,900万人でピークを迎え、その後も、75歳以上の人口割合は上昇し続けることが予想されています。
このような状況の中、団塊の世代(約800万人)が75歳以上となる2025年(平成37年)以降は、国民の医療や介護の需要が、さらに増加することが見込まれています。
このため、厚生労働省においては、2025年(平成37年)を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築を推進しています。
ウェブサイトに掲載された「地域包括ケアシステムの姿」を表すイメージ図には、住み慣れた地域でいつまでも元気に暮らすための生活支援・介護予防を担うものとして「老人クラブ、自治会、ボランティア、NPO等」の地域での活動があげられています。
少子高齢化がさらに進む日本では、こうした体制を築いていくことは不可欠だと感じます。しかし、その上で、地域包括ケアシステムが語られる文脈では高齢者の存在が社会問題として語られているような印象を受けてしまいます。
高齢化がさらに進めば介護職員が不足し、財政難のため介護保険料も上昇してしまう、と。意地の悪い見方をすれば、社会問題を乗り越えるために「老人クラブ、自治会、ボランティア、NPO等」の地域にある資源を動員しようとするのが地域包括ケアシステムだと言えなくもありません。
「居場所ハウス」に限らないと思いますが、草の根の活動として運営されている「まちの居場所」をはじめ、地域における具体的な種々の活動において、一人ひとりの高齢者はかけがえのない存在。一人ひとりの存在は決して(社会)問題ではない。
しかし、どのような制度を組み立てるかという、言わば上から社会を俯瞰する視線をとった時には、高齢者の存在が社会問題と見なされてしまう。
地域包括ケアシステムの意義を語ろうとすると、高齢者の存在が社会問題であるということから話が始まってしまう。この部分に根本的な問題があり、この部分を乗り越えないと「老人クラブ、自治会、ボランティア、NPO等」の地域での活動が社会問題を解決するための手段として利用される恐れがあるのではないか。
高齢者の存在を社会問題として語るのか、語らないのか。些細なことに思われるかもしれませんが、行政と地域の連携を考えていく上では、この立ち位置が決定的に重要なポイントだと思います。
一人ひとりの高齢者の存在を(社会)問題としないこと。これが地域における具体的な活動がもっている価値であり、この価値を損なってしまってはならない。こうした価値を大切にすることからしか、一人ひとりの存在を問題化してしまう社会とは何か? を問うことは始まらないと思います。