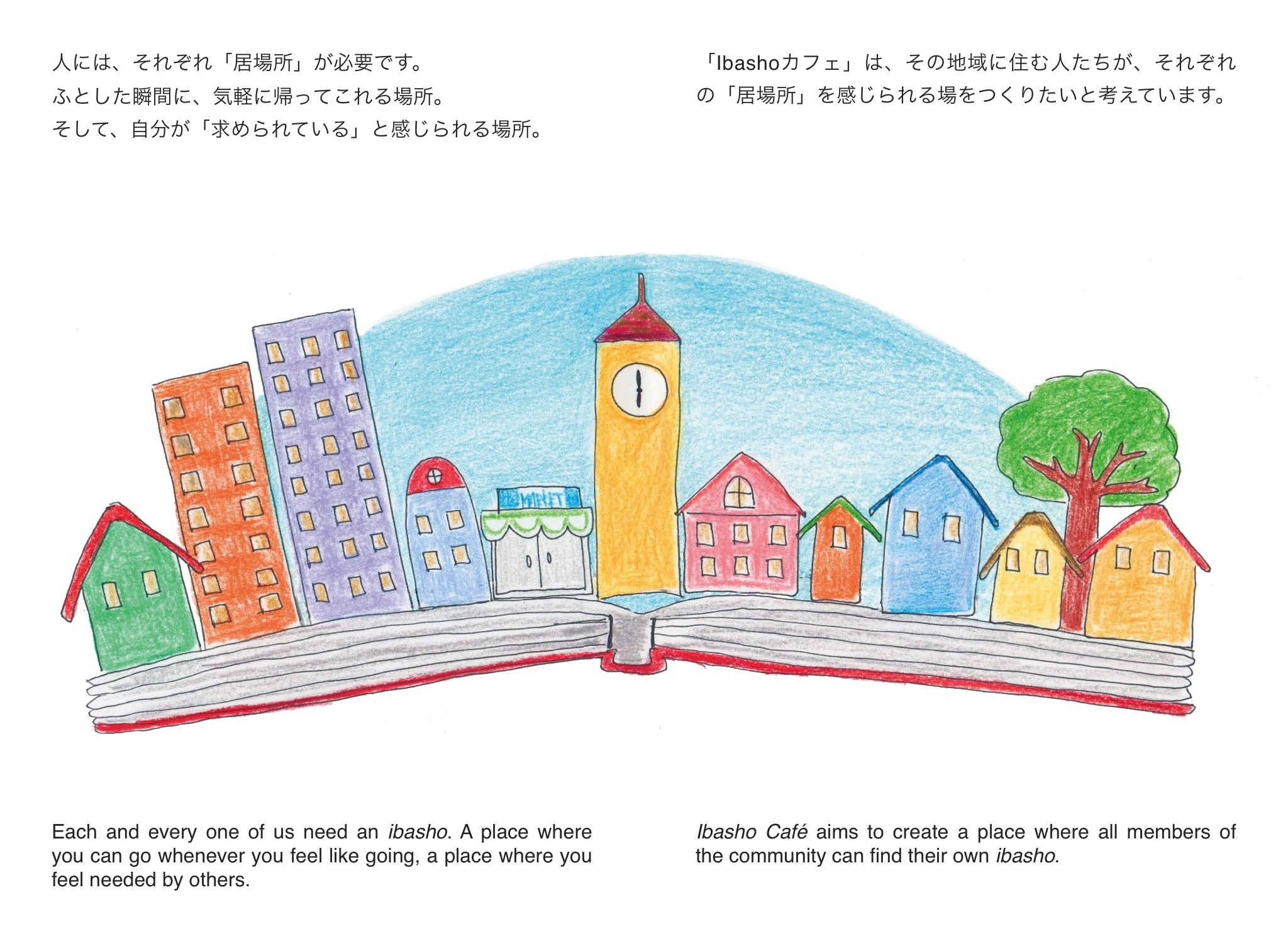2016年12月21日(水)、東京大学大学院工学研究科にて復興建築計画論の講義が開催されました。この日の講義では、Ibasho/Ibasho Japanの代表である清田英巳さんが講演。講演の内容はワシントンDCの非営利団体Ibashoを立ち上げた理由と活動の目的について、そして、岩手県大船渡市の「居場所ハウス」、フィリピンのバゴング・ブハイ(Barangay Bagong Buhay)でのIbashoフィリピン、ネパールのマタティルタ村(Matatirtha)でのIbashoネパールについてです。
この講義に、大船渡の「居場所ハウス」の運営のサポートとフィールドワークを続けている者として参加させていただき、「居場所ハウス」の近況の補足説明と、質問への回答をさせていただきました。
東日本大震災から5年半が経過し、資金がなくなった、親団体/本部からの資金援助がなくなったなどの理由で活動を停止する団体が出始めている中で、「居場所ハウス」は地域住民が主体となって活動の継続が考えられている1つの例だと考えています。
この日の講義での質疑応答を通して、「居場所ハウス」が継続されている要因について次のようなことを考えました。
1点目は、海外からの提案をきっかけとして開かれた「居場所ハウス」が、地域住民の場所になったかについて。
この点については、地域の人々がオープン後に、運営のために支障となっていた柱を切った、勝手口を設置した、屋外に食堂を建設したなど、区間に手を加えたというのが大きいと思います。空間に手を加えることを通して、「居場所ハウス」が自分たちが思い描いたものへと目に見えるかたちで変化していく。この意味では、オープン時点では建物は完成していなかったと言えるかもしれません。
ここからは、場所をオープンすることに対する見方を変えることが意味をもってくると思わされます。つまり、オープンというのは大きな節目であるのに違いないが、オープン前、オープン後というように明確に区切るという考え方を脇に置いてみる必要があるのだと思います。
2点目は「居場所ハウス」では仮設住宅に住んでいる人が来たり、以前仮設住宅に住んでいた人が同窓会を開く場所になっていることについて。
仮設住宅に住んでいる/住んでいた人々に来てもらえる場所になっていることは、「居場所ハウス」が被災地において復興の拠点としての役割を担っていることの1つの現れだと考えます。
仮設住宅にも集会所がありましたが、仮設住宅の集会所は仮設住宅の住民が訪れる場所であり、周囲の人が行きにくい雰囲気になっていた。また、一度仮設住宅から転居した人にとっても行きにくい場所となっていた。「居場所ハウス」は仮設住宅に住んでいる人も、そうでない人も訪れることができる場所になっていることの背景には、「居場所ハウス」が被災者のための場所であることを過度に打ち出してこなかったからだと言えます。
仮設住宅との連携により、仮設住宅の住民以外の人が訪れにくい場所になってしまう恐れがあるとすれば、仮設住宅とは距離をおいた場所であることにも意味があると言えます。
復興や地域包括ケアの文脈においては様々な活動や場所が連携することの必要性が言われますが、ここで見てきたようにあえて連携せず、別の種類の場所にしておくことにも意味があると言えます。
この日の講義では「居場所ハウス」のような場所に対する研究についての議論もなされました。研究者が、「居場所ハウス」のような場所の効果を述べることについて、です。
この点については、「居場所ハウス」のような場所の効果を誰に向けて語るのかを考える必要があるのではないかという話をさせていただきました。
先入観にとらわれず、客観的なデータにもとづいて効果を語るという研究者の役割は大きいと思いますが、その語りは、自分たちで活動を振り返るためなのか、他で同じような活動をしたいと思う人に説明するためなのか、行政に説明するためなのか、あるいは、研究者同士で議論するためなのか。
この点についてまだ自分自身が答えを持ち合わせているわけではありませんが、研究の成果を、誰を宛先として語るのかについて議論する必要があるのではないかという話をさせていただきました。