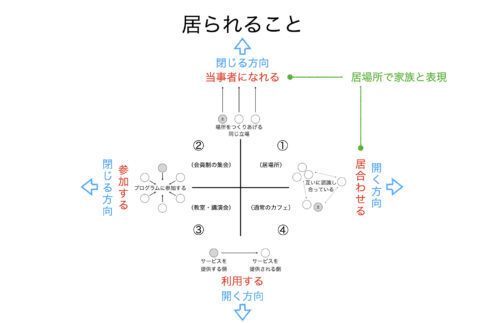2021年12月12日(日)、府中市市民活動センター・プラッツ主催の「第三の居場所:地域のたまり場・コミュニティカフェを知ろう」という講座で、「まちの居場所の紡ぎ方」と題して、大阪府千里ニュータウンの「ひがしまち街角広場」、岩手県大船渡市の「居場所ハウス」を中心に、居場所にはどのような特徴があるのか、何が居場所の魅力なのかという話をさせていただく機会がありました。
講座は家でも職場でもない、第三の居場所の意義や実際の事例を知るという目的で企画されたもので、居場所に対して既に何らかのかたちで関わっておられる方、これから居場所を開きたいと考えておられる方などの参加がありました。
講座でいただいた質問により、改めて居場所について考えるきっかけをいただきました。以下は、講座終了後に居場所について、特に主客の関係について改めて考えた内容です。
居場所ハウス
「居場所ハウス」は、何歳になっても自分にできる役割を担いながら地域で暮らし続けることの実現という「Ibashoの理念にもとづいて運営されていますが、実際、運営には高齢者が様々なかたちで関わっています。
その1つが、特技を活かすというかたちでの運営への関わり。
食堂での調理、花や植木の手入れ、大工仕事、パソコンを用いた事務作業、買い物送迎のマイクロバスの運転など、スタッフの中には様々な特技を活かして運営に関わっている人がいます。

スタッフでない人にも、特技を活かした関わりがあります。「居場所ハウス」では料理、そば打ち、生花、絵手紙、竹とんぼ、布ぞうりなど様々な教室が開かれていますが、教室の講師は主に地域の高齢者に依頼。

「居場所ハウス」を通して、地域には様々な特技をもつ人がいることに気づかされます。「居場所ハウス」が地域には様々な特技をもつ人の存在を可視化していると捉えることもできます。
このように何らかの特技をもっていることは「居場所ハウス」に関わるための大きなきっかけになっていますが、見落としてならないのは、「居場所ハウス」への関わりのかたちは必ずしも特技を活かすことだけに限定されるわけではないということです。
「居場所ハウス」に日常的に来られていた90代のある女性は、自分には何もできないからと、時々、砂糖や小麦粉をリュックに背負って持って来てくださっていました。

「居場所ハウス」では毎春、高田人形という地域に昔から伝わる土製の人形を何人かからお借りして展示しています。高田人形を貸してくださったのは、「居場所ハウス」に日常的に来られていた80代の女性で、この女性は「居場所ハウス」のスタッフらが高田人形の話をしていたのを耳にして、それなら家のどこかにしまってあると言って、探して持って来てくださいました。高田人形は、何十年かぶりに取り出したようで、この女性は「お雛さんも、みんなに見てもらって幸せだなぁ」と話されていました。

この他にも、食事を屋外のキッチンから運んだり、食べ終えた食器を洗ったり、他の来訪者にお茶を出したり、薪ストーブに薪をくべたりして、運営を助けてくださる方がいます。
このようなかたちでの関わりは、特技を活かすとまでは言えないかもしれません。しかし、自分にできる役割を担うことで誰かの役に立てるという点で違いはありません。社会では、高齢者はしばしば役に立たない存在だと見なされるため、何歳になっても誰かの役に立てる(という手応えを得られる)ことは、地域で暮らすうえで非常に大切なことだと考えています。
それでは小麦粉や砂糖を持ってくる、高田人形を貸す、食器を洗うなど、特技を活かすとまでは言えないことが、結果として誰かの役に立つことにつながるのはなぜなのか。それは、「居場所ハウス」という場所(施設ではない場所)があるからではないかと考えています。場所があることで、他者に貢献することが可能になる。つまり、場所は誰かの役に立てることのハードルを低くしている。
かつての日本では、隣近所で醤油を貸し合うことが行われていたという話を聞きます。醤油を貸すことも特技を活かすとまでは言い切れませんが、隣近所という具体的な場所に基づく関係が築かれていれば、醤油を貸すというちょっとしたことを通じてでも誰かの役に立つことができる。これも、「居場所ハウス」での出来事と通じるものがあると考えています。
現在社会ではこうした場所が弱まりつつある。そして、場所は誰かの役に立てることのハードルを低くしているとすれば、逆に、現在では他者に貢献することのハードルが高くなっているのかもしれない。このことが、地域に関わることを難しくしている大きな背景ではないか。
府中市市民活動センター・プラッツ主催の講座には、居場所(コミュニティカフェ)を開きたいという方が参加されていました。この方は、居場所(コミュニティカフェ)を開くためにセミナーなどに参加されたようですが、セミナーで自分から提供できる何かがないといけない、他の人と違う何か尖ったものを作らないといけないと言われたとのこと。けれども、それには少し違和感を感じたという話をされていました。
特技を持っていること、その特技を活かして誰かの役に立てることは素晴らしいことです。しかし、特技を活かすことだけに焦点が当てられる社会とは、人を有用性の側面からのみ評価する不自由なものかのしれません。
先日の講座では、90代の女性が「居場所ハウス」に砂糖や小麦粉を持って来ていることに触れて、役割があるとかそういうことではなくて、自分にできることと言ってこのような関わりが自然に発生するのが居場所の魅力だと思う。それでは、このような関わりが自然に発生するような場所を実現するために、スタッフはどのようなことを大切にすればよいのかという質問をいただきました。
この質問に対しては、スタッフが相手に、先回りして何かをしてあげることを少し控えてみること、少し待ってみることを心掛けるのが大切ではないかという話をしました。
居場所のスタッフは、自分がしたことが誰かの役に立つこと、誰かに喜んでもらうことに喜びを感じる方が多いと思います。そして、他者に対して様々な配慮をされる方が多いと思います。しかし、先日の講座では、スタッフは無意識のうちに「人を集めないといけない」と考えたり、「ぜひご来場ください」みたいな感じで待ち構えてしまうことがあると話された方がいた通り、スタッフは様々な配慮ができるがゆえに、先回りして相手に何かをしてあげるという構えになってしまうことがあるかもしれません。
例えば、90代の女性が砂糖や小麦粉を持って来ることに対して、砂糖や小麦粉をリュックで背負って持って来るのは重くて大変だし、転ぶと危ないからと言って断ることも可能。しかし、先回りするのを少し控えて、「ありがとう」と相手を受け入れること。これが、自分にできる役割を担える余地を生み出すことにつながっているように感じます。
ひがしまち街角広場
「ひがしまち街角広場」においても、スタッフと来訪者との関係を緩やかにすることが意識されており、例えば、スタッフが忙しい時には来訪者が食器を洗ったり、他の来訪者のところに飲物を運んだり、テーブルを片付けたりすることが行われています。逆に時間があるときには、スタッフと来訪者が一緒に話をしている。

「ひがしまち街角広場」ではコーヒー、紅茶などの飲物が100円の「お気持ち料」で提供されていますが、スタッフの方から来訪者の注文を聞くことは行われていません。「ひがしまち街角広場」の初代代表の女性は次のように話されています。
「かと言って、何も来られた方に『何出しましょ』とはこちらからは聞きませんし。何も注文しないで、1時間喋って帰られても、それはそれでいいわけですから。ほっとくって言うか、こちらから注文聞きに歩いたり、そういうことはもう一切してません。向こうから言われたら。人によっては、『ここは来て、何も言えへんかったらほっとかれる』っていう人もいるんですけど、『そうなんですよ、ここはほっときますよ』言ってね、そういう冗談も言えるような場所ですから。」
「ひがしまち街角広場」の来訪者は、自分から何が飲みたいかを伝える必要がある。このことは、「何も注文しないで、1時間喋って帰られても、それはそれでいい」と話されているように、必ずしも飲物を注文しなくてもよいという余地を作り出しています。
先にご紹介した通り、先日の講座では居場所のスタッフは無意識のうちに「人を集めないといけない」と考えたり、「ぜひご来場ください」みたいな感じで待ち構えてしまうことがあるという話が出されました。それでは、「ひがしまち街角広場」のスタッフはなぜこのような思いに駆られることなく、来訪者の方から注文があるまで待つことが可能なのか。初代代表の女性は次のようにも話されていました。
「一生懸命エプロンかけて待機してても、誰も来てくれなかったら『街角広場』の意味がないんです。『街角広場』に誰も来なくなったら補助金もらうのではなく、そうなった時には『街角広場』は閉めようと。地域のみなに必要とされてないものは潔く閉めましょうといつでも言ってます。」
「補助金ももらってないし、営業努力をしなくていいんですよね、『街角』は。誰も来ないことはないんですけど、今日は少ないねって言っても、ちっとも自分たちはしんどくない。」
「ひがしまち街角広場」は2001年9月30日のオープンから半年間は、豊中市の社会実験として補助を受けて運営されていました。そして、社会実験が終了し、住民による「自主運営」が始まってからは補助金を一切受けず、飲物の「お気持ち料」と、夕方以降・定休日の会場使用料によって家賃、光熱水費、食材費など全ての費用を賄っています。このようなかたちで運営されてきた背景には、「地域のみなに必要とされてないものは潔く閉めましょう」と話されていたように、地域の人が訪れないような場所を補助金を受けてまで続ける必要はないという考えがあります。
結果として、補助金を受けることなく約20年間の運営が継続されてきましたが、補助金をもらっていないから営業努力をしなくていい、たとえ誰も来なくても自分たちはしんどくないという初代代表の言葉は重要です。
補助金を受けて運営していると、どのような活動をしたのか、何人が訪れたのかという実績が評価されることになります。そのため、スタッフは無意識のうちに「人を集めないといけない」と考えたり、「ぜひご来場ください」みたいな感じで待ち構えてしまう。それが、先回りして何かをしてあげることを少し控えてみること、少し待ってみることを困難にし、自分にできる役割を担える余地ををなくしてしまうことにつながってしまう。
もちろん、居場所に補助金は不要だと言うつもりはありません。補助金が意味をもつ場面もあると思います。だからこそ、スタッフは先回りして何かをしてあげることを少し控えてみること、少し待ってみるという余裕をもつことを意識することが一層必要になるのかもしれません。このことは些細なことのように思われるかもしれませんが、この積み重ねが居場所の雰囲気を作りあげると考えています。