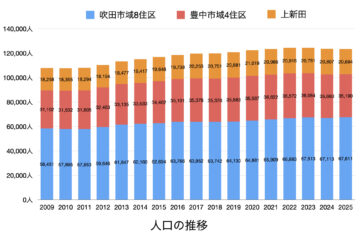2024年9月7日、タワーホール船堀で開催の「第28回『とぽす』とその仲間展」の会場で、「親と子の談話室・とぽす」(以下、「とぽす」)のドキュメンタリー映画『とぽす~豊かな交わりの場所として~』(豊島仁監督、2024年)の上映会が開かれました*1)。

(「第28回『とぽす』とその仲間展」)
「とぽす」を初めて訪れたのは2003年3月31日。それから何度もお伺いしてきましたが、映画をみて、「とぽす」の広がり、深さに改めて気づかされました。




(最近の「親と子の談話室・とぽす」の様子)
新しいコミュニケーション
「とぽす」は1987年に、白根良子さんの、思春期の子どもたちにはゆっくりできる場所、さまざまな大人と接することのできる場所が必要だという思いをきっかけに開かれた場所。当時は校則が厳しく、学校帰りに友だち同士で道端で立ち話をすることすら禁止されていた。子どもたちは自分と利害関係のある両親と学校の先生としか接していなかった。当時の子どもを取り巻く状況はこのようなものだったと伺いました。
このような状況を背景として開かれた「とぽす」には、オープンから37年間にさまざまな人々が訪れてきました。この変化を白根良子さんは次のように話されています。
「その目的が、最初は芽だったんだけど、それが少しずつ伸びていって、枝をはって、実がなっていくみたいな。・・・・・・。私は、子どもと大人のコミュニケーションの場所であるということ。子どもと大人っていうのは年齢の差もある。それに付随して、差別とかそんなものを感じるものを全てとっぱらいちゃいたいっていうね、そこまでいってここをつくったので。それを新しいコミュニケーションと私は名づけたんだけど、それしか言葉としてはね、表現できなかったので。『いま新しいコミュニケーション〔の心〕を考える』んだから、まだ考え続けてるんですよ。その中に、心の病の人とのコミュニケーション、知的障害の人とコミュニケーションも生まれてきたし。」
「とぽす」における「新しいコミュニケーション」というのは、「年齢、性別、国籍、所属、障害の有無、宗教、文化等、人とのつきあいの中で感じる『壁』を意識的に取り払い、より良いお付き合い」をするという意味*2)。誰にも年齢、性別、国籍、所属などの多くの属性があります。これらの属性は、ある場合には、生きるうえでの拠り所になることもある。けれども、これらの属性に押し込められ、画一的な存在と見なされることもある。自分自身も、目の前にいる相手をこのような属性によって評価してしまうことがある。この場合、これらの属性は相手と付き合ううえでの壁になっている。
「とぽす」では、当初からこのような壁を取り払った「新しいコミュニケーション」を実現するという目的が掲げられてきましたが、オープン後にこの場所を訪れてきたさまざまな人々との関わりが、その具体的な姿となることで、「新しいコミュニケーション」は徐々に豊かな意味をもつものとして育ってきた。このような変化を、白根良子さんは「最初は芽だったんだけど、それが少しずつ伸びていって、枝をはって、実がなっていくみたい」と表現されているように思います。
「一人の人間として」いることができる
「とぽす」では、運営を通してさまざまな人々との「新しいコミュニケーション」が生まれてきましたが、映画を見て、「新しいコミュニケーション」にはこれとは別の側面があることに気づかされました。
映画の中で、ある方が、「新しい出会いのコミュニケーションでなく、常に会ってる人と新しいものをお互いにつくっていく」、「同じメンバーでも、常に新しい気持ちを、その都度リフレッシュしながらお付き合いさせていただいてる」と話されていたように、「新しいコミュニケーション」には、いつも顔をあわせている相手とのコミュニケーションにおいて、新しさを見つけていく、つくっていくという意味もある。
「人と人との交わりっていうのは、相手の気持ちを思いながら、ゆっくりと長い時間をかけて紡ぎあげていくものだと思うんですね。『今、あなたの言ってることはわからないよ』って突っぱねるんじゃなくて、長いお付き合いをしましょうという。そういう気持ちでお付き合いしていけばいいのかな。」
目の前にいる相手には、たとえいつも顔をあわせている相手だとしても、自分にとって知らない側面がある。だから、自分の今の枠組みによって相手との関わりを拒絶したり、自分の今の枠組みの範囲で相手を理解した気になったりしないこと。映画の中で、「一人の人間として、当たり前のことですけど、病気なのか病気でないのかとかあまり問題ならずにここにいれる」と話されている方がいましたが、さまざまな属性を解いた「一人の人間として」いることができることが、「とぽす」の居心地の良さだと感じます。
「今日来たお客さまには、精一杯、ここに来たらゆったりしてもらえるっていう、それが目標ですね。あまり大きなことっていうのはないですね。なぜか、『あぁ、ここに来てほっとしたわ』、『今晩何にする?』なんて言って、『今晩、何だか決まってないわ』なんてしゃべりながらでも、夕食をつくる元気が出るんですね。」
「とぽす」は属性を解いて「一人の人間として」、ゆったり、ゆっくりできる場所であることが、ささやかな日常について語られたこの言葉にも現れています。
そして、自分の今の枠組みを相手に押し付けないという関わり方は、白根良子さんが「とぽす」を開く前から続けてこられたのだと、映画を見て気づかされました。白根良子さんは、「とぽす」を開こうと考えるようになった当時の状況を次のように話されています。
「中学生ぐらいで進路指導をやり出したんですよ。だんだん大人になって、高校生ぐらいになって、色んな人と交わっていって、自分がこういう職業につきたいんだと思うんだろうけど。中学1年生で、『お前は大きくなって何になるの?』という授業が、授業参観の時にあったんですよ。その時に私は、『何になりたいったって、私なんか中学の時に何になりたいなんていう、希望も何もなかったな』と思ったんですよ。だとしたら、もっと色んな職業をもっている大人に出会わなきゃ、自分が何になりたいかなんてわかりやしないじゃないかって思ったのもありましたね。」
「お前は大きくなって何になるの?」という問いかけは、子どもの希望を聞いているようでいて、実は、大人が自分の理解できる枠組みの範囲での答えを暗に求めるものになっていないか。だとすれば、この問いかけは、子どもを大人が理解できる枠組みに押し込めてしまうという意味で、子どもにとって酷ではないのか。白根良子さんは、このようなことを話されていたのかもしてません。
次に紹介するのは、白根良子さんの中学校の教員時代の出来事。この出来事が大きなきっかけとなり、白根良子さんは中学校の教員を辞めて、神学校に入学されました。「とぽす」において、表の桜並木との関係が大切にされていることにも関わる出来事です。
「私のクラスの受けもちになった一人の女の子が、『先生、毎年、毎年桜はきれいに咲いて、そして散るよね、人間も死ぬんだよね。どうして人間は死ぬんだろう』って言った時、私は説明できなかった。何よりも中学校一年生の子が人間の死っていうことを桜を見ながら思うのかと、私よりはるかに大人だって思って。そういう子どもたちに、人生のことについてもっと深く、お互いに話し合う人になりたいと思ったんですね。」
目の前にいる相手に、自分の今の枠組みでは応えることができない。だから自分の枠組みを変えようとすること。白根良子さんがずっと続けてこられたことです。
「とぽす」という空間
目の前にいる相手には、自分にとって知らない側面がある。だから、自分の今の枠組みを相手に押し付けないことが大切にされている。ただ、これは逆に表現すべきなのかもしれません。相手に自分の今の枠組みを押しつけないという関わり方を大切にするからこそ、相手の新たな側面を発見できる、というように。
「新しいコミュニケーションっていうのは、時代とともに変わると思うけれど、人としてお互いに心を開きあってコミュニケーションすることがとても大切なんだと私自身はわかってきたし、ここに来られてる方もそれが一番大切なことなんだってわかってきてくださってると思います。」
「とぽす」では一人ひとりが「新しいコミュニケーション」を大切にしている。それと同時に、「とぽす」という空間自体が人々の緩やかな関わりを許容するというかたちで、「新しいコミュニケーション」を支えるようなつくり方がされているのではないか。
例えば、テーブル。「とぽす」にさまざまな大きさ、形、高さのテーブルが置かれているのは、それぞれが自分のテーブルで過ごしていても、周りから孤立していない状況をつくるという考えから。白根良子さんは、このような状況を「空気がまわる」と表現されています。
「お互いにそれぞれが自分のところに座ってて、誰からも見張られ感がなく、ゆっくりしてられるっていう。だけども、『何か困った時があったよね』って言った時には傍にいてくれるっていう、そういう空間って必要だなぁと思ってね。」
「孤立しないでいられる空間。だけど他人から介入されないで、安心していられる空間。そっちにぽつんと一人で座っていても、みんながいるから安心だ。だけど、こっちにいるみんなは自分を侵害しないよっていう場所。」
映画の中で「一緒にいるんだけど、ちゃんと自分としてもいれる」と話されている人がいましたが、「とぽす」の空間に込められた思いが、実現されていることがわかります。テーブルのほかにも、桜並木を見渡せる窓、鳥の翼の下に守られているような形の屋根など多くのことが考えられていますが、「とぽす」に置いているものについて次のように話されています。
「自分の家にいるようなゆったり感を出したいということで、きっちりと物を揃えておくんじゃなくて。もちろんお花はいつも飾る。それから私が拾ってきた石とか、私が描いた絵とか、私がいいと思った絵を飾ったり。それからどうしようもないような枯れた草とか、木とかを、石や木が、『ここに置いてね』って言ってくれるところに置くというか、そんな場所のつくりかたをしています。」
花や絵は価値があって、石、枯れた草や木は価値がないというのが一般的な見方かもしれません。けれども、それこそが既存の枠組みによる見方ではないか。「とぽす」では、全てが「『ここに置いてね』って言ってくれるところ」に置かれている。「とぽす」に置かれたものが、「新しいコミュニケーション」が実現された具体的な姿になっていると言えそうです。
居場所として、創造の場所として
今は目の前の相手のことを理解できなくても、自分の今の枠組みを相手に押し付けずに、長い時間をかけて付き合っていく。その結果として、相手を理解できるようになる。このプロセスにおいては、実は自分の枠組みも変えられているのであり、この意味で、自分の新たな側面を発見することだとも言える。
「とぽす」は、人々が「一人の人間として」いることができる居場所であると同時に、創造の場所でもある。このことの意味を今まで十分に考えてきませんでしたが、自分の新たな側面を発見していくことが、「創造しようという意欲」の源泉になっているのではないか。そうだとすれば、「とぽす」においては居場所であることと、創造の場所であることは不可分なのだと、映画を見て気づかされました。
「『とぽす』という場所があるから創造しようという意欲が湧いてくる。・・・・・・。『とぽす』ってやる気を起こさせる場所だと思うんですね。ウクレレなんてやったことがない方が、『僕は絵は苦手だからウクレレです』とか。折り紙を始めたり。ここに来る人との出会いを通して、自分は何がやりたいって考えるようになるのかな。私も、『とぽす』がなかったら、本気になって絵を描くようにならなかったかもしれない。」
「『とぽす』という空間の中で、お互いを認め合える、お互いのマイナスな点も認め合える。そのことで自分を自分として認めることができる。そういう根っこがないと創作っていうのはできないと思うんですよね。何をつくりたいか、何のためにつくるのかっていうことが、コミュニケーションの中で少しずつ少しずつ育ってきて、絵を描こうとか立体をつくろうとか、そしてそれを発表してみんなに見てもらって作品にしようというね。見てもらわないとね、作品にならないでしょ。」
「新しいコミュニケーション」とは、相手を「一人の人間として」認めることであると同時に、自分自身の枠組みが変わり、自分の新たな側面を発見していくプロセスでもある。この新しさの発見が「創造しようという意欲」になる。さらに、創造したものを、既存の枠組みを取り払って認めてもらえるという信頼感があるからこそ、創造したものを見てもらおうと思えるようになる。これが、数々の「作品」を生み出していく。
「とぽす」を継ぐということ
映画の後半で、「とぽす」をどう継ぐのかという話が取りあげられていました。継ぎたいという思いはある、けれども、具体的にどうやって継いだらいいのか。全く同じ人間でないので、意志を継ぐとはどれぐらいの意志のことをいうのか、と。
37年という歴史が豊かであるがゆえに継ぐことが重い。もちろん、ここで外部の者が「とぽす」を継ぐことについて何か言える立場ではありませんが、白根良子さんの次の言葉が思い起こされます。
「自分が自由に発言できる、意識的に障害を取り払ってコミュニケーションをする場っていう、そのスタンスだけが変わらなければいいなと思いますね。」
自分の今の枠組みを相手に押し付けるのでなく、長い時間をかけて付き合っていこうとすること。それによって、自分もまた変わっていくこと。このような「新しいコミュニケーション」は、言葉でいうほど容易でないように思えます。しかし、白根良子さんは、これは難しくないんだと話しておられるのかもしれません。
「毎日、毎日、出会う人を大切に、宝物のようにお付き合いしていく。その連続が『とぽす』を支えてきたのではないかと思っています。人っていうのは、お互いに自分の心を通いあわせたいという気持ちを誰でももってる。でも、自分の気持ちを素直に表現できる方もいれば、なかなか表現できない方もいらっしゃる。表現がオーバーになったり、自分の寂しさや何かを隠すために心と裏腹な言葉を喋ったりすることもあるけれど、人と人との交わりっていうのは、相手の気持ちを思いながら、ゆっくりと長い時間をかけて紡ぎあげていくものだと思うんですね。」
自分の気持ちを素直に表現できる人もいれば、そうでない人もいる。けれども、誰もが「お互いに自分の心を通いあわせたいという気持ち」をもっている。これは、他者と向き合う時の構えについて話されているように思いました。誰もが「お互いに自分の心を通いあわせたいという気持ち」をもっているという他者への信頼感が、「新しいコミュニケーション」の第一歩を踏み出すための背中を押してくれるということ。そして、一歩踏み出した後は、「毎日、毎日、出会う人を大切に、宝物のようにお付き合いしていく」ことを続けていけばいいんだと。
このようにして、「とぽす」で紡ぎあげられてきたかけがえのない関係が、映画には記録されています。
■注
- 1)現在、ドキュメンタリー映画『とぽす~豊かな交わりの場所として~』はこちらで公開されている。
- 2)『とぽす通信』・「『とぽすとその仲間展』第18回記念号」(2011年)より。