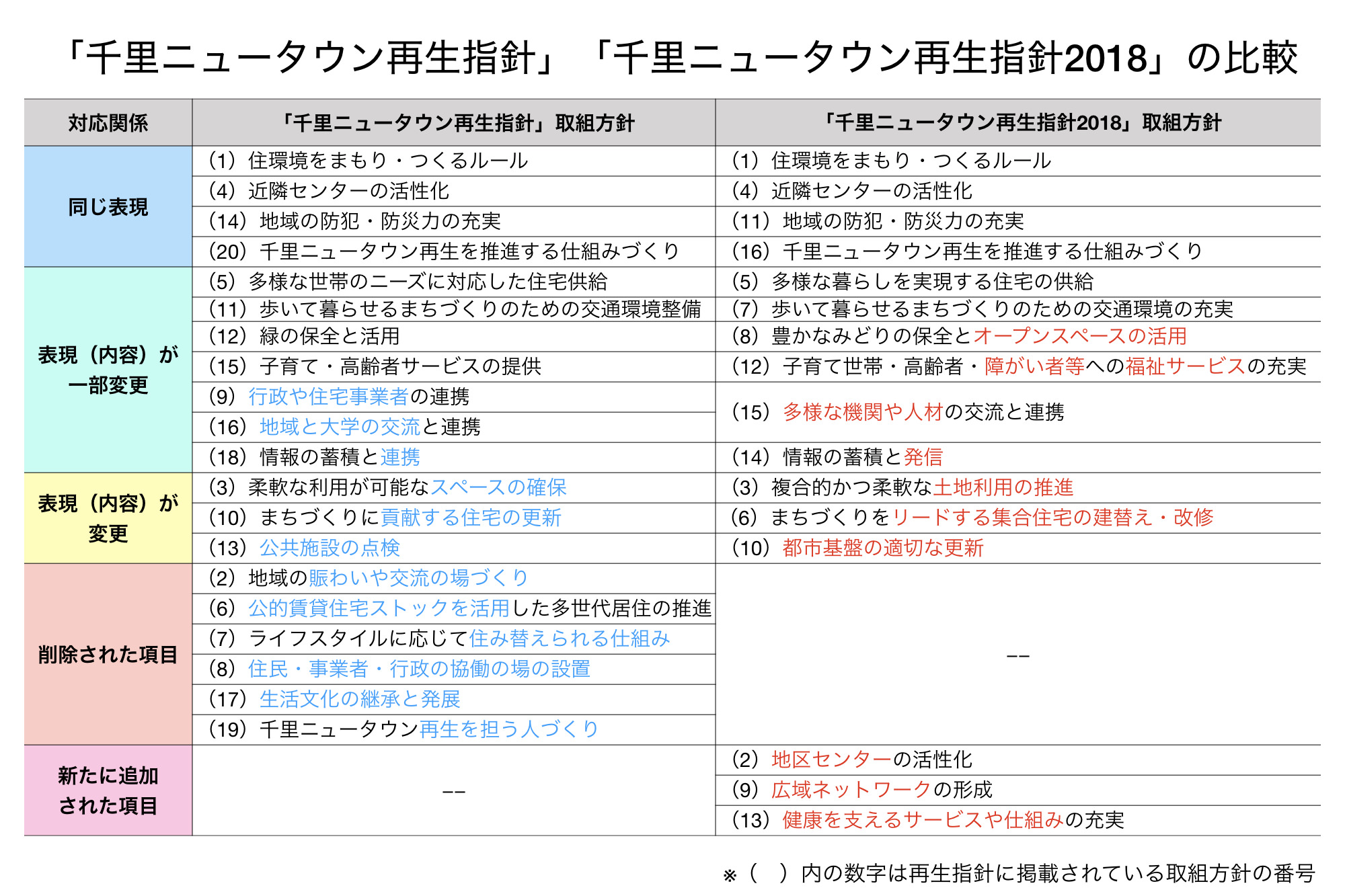ニュータウンらしい光景として、集合住宅や戸建住宅が整然と建ち並ぶ光景をあげることができますが、道路にもニュータウンの特徴が現れています。1つの敷地内の建物であれば、ニュータウンであるか否かに関わらず計画できますが、道路の計画というのは街全体を計画するニュータウンならではと考えれば、ある種の道路はニュータウンらしい光景を作り出していると言えます。ここでいうある種の道路というのが、歩行者専用道路です。
千里ニュータウンの歩行者専用道路
千里ニュータウンは近隣住区論にもとづき12の住区が開発されましたが、前半に開発された住区(佐竹台、高野台、津雲台、古江台、藤白台)と、新住宅市街地開発法(新住法)に基づいて開発された新千里北町以降の後半に開発された住区(新千里北町、新千里東町、桃山台、竹見台、新千里西町、新千里南町)では道路の作り方が異なっています。それが、歩行者専用道路による歩車分離の試みです。歩車分離とは、歩行者の安全を確保するために、人が歩く道と車が走る道とを分けること。
前半に開発された住区では、クルドサック(袋小路)が採用されましたが、団地、戸建住宅地それぞれの中での歩車分離がなされているものの、住区全体での歩車分離はなされていませんでした。しかし、新千里北町以降の住区では、近隣センター、学校、鉄道駅、公園など住区内の主な場所が歩行者専用道路、つまり、車が通らない道によって結ぶことで、住区全体での歩車分離が計画されました。
新千里北町で初めて採用された歩行者専用道路は海外の事例を参考にしたものですが、開発に携わられた方の話では、当時日本にはフットパスのような短い歩行者用の道路はあったものの、歩行者専用道路というものが存在しなかったため、歩行者専用であるという認識を共有するところから始めなければならなかったということです。


(新千里北町の歩行者専用道路)

(桃山台の歩行者専用道路)
歩行者専用道路と車道は、横断歩道によって交差(平面交差)するのでなく、歩行者専用道路が車道の上を跨ぐ、あるいは、歩行者専用道路が車道の下をくぐるという立体交差による歩車分離が考えられています。普通、橋というと川の上に架けられたものを思い浮かべますが、千里ニュータウンには車道の上に架けられた橋が多数あります。
千里丘陵に開発された千里ニュータウンでは、尾根筋に歩行者専用道路、谷筋に車道を通すことで、一般的な歩道橋のように階段やスロープを上り下りすることなく車道を越えることができるという工夫もされています。

(新千里北町のすずかけ橋)

(竹見台/桃山台間のにれのき橋)
新千里北町の次に開発された新千里東町では、歩行者専用道路について新たな試みがなされました。1993年に市民公募によって「こぼれび通り」と名付けられた東町公園の南側を通る歩行者専用道路は、歩行者専用道路内に植栽帯がもうけられています。植栽帯に植えられた木々は木陰を作り出し、所々にベンチが置かれており、歩いていて気持ちのよい道。「こぼれび通り」は、後に全国のニュータウンや大規模住宅地に導入されることになる「緑道」のモデルになった歩行者専用道路であり、日本のニュータウン計画史において重要な位置づけの道路です*1)。


(新千里東町の「こぼれび通り」)
最近、泉北ニュータウン(大阪府堺市)、千葉ニュータウン(千葉県白井市・船橋市・印西市)を歩く機会がありました。一部のエリアを少し歩いただけですが、歩行者専用道路について次のような光景が印象に残っています。
泉北ニュータウンの歩行者専用道路
大阪府堺市の泉北ニュータウンは、日本で2番目に開発された大規模ニュータウン。まちびらきは、千里ニュータウンが1962年、泉北ニュータウンが1967年と5年の違いがあります。
泉北ニュータウンは、大きく泉ヶ丘、栂、光明池の3地区に分かれていますが、それぞれの地区では近隣センター、学校、鉄道駅、公園などが「緑道」と呼ばれる歩行者専用道路によって結ばれています*2)。
千里ニュータウンと泉北ニュータウンの違いについて、次のように説明されています。
「さらに千里と異なる計画の大きな特徴は、自然環境の保全と緑地の構成にある。新住事業では開発利益を周辺に及ぼすことを避けるために周辺緑地を設けることとし、千里もこれに従っているが、泉北では地区内の優れた自然環境を最大限に保存・活用することとし、緑地を各地区の中央部に集中させ、広幅員(20~40m)の緑道としてネットワークすることで、自然と共存する都市の実現を図っている。主要なコミュニティ施設はこの緑道に沿って配置されている。事前の植生調査に基づき、希少な林や景観上重要な現況植生をできる限り緑道に組み入れて保存するとともに、まとまった風致公園や都市緑地を設定している。こうした試みも泉北から開始されたものである。」
「泉北ニュータウンの住区設計では、マスタープランの担当者と企業局から委託された土木、造園、給排水計画の専門家が一つのチームを編成して、各要素の相互調整を図りつつ計画策定を進める体制がとられた。これも千里との大きな違いで、これによって諸計画の整合性が図られ、住区設計の水準を大きく向上させることが可能となった。」
※佐藤健正・(株)市浦ハウジング&プランニング『日本のニュータウン開発と(株)市浦ハウジング&プランニングの取り組み』(株)市浦ハウジング&プランニング, 2016年3月15日

(槇塚公園付近)

(茶山公園付近)

(茶山台近隣センター付近)

(茶山公園付近)
泉北ニュータウンでは、千里ニュータウンの歩行者専用道路を思い起こさせる光景を見かけた一方で、千里ニュータウンとは異なる光景も見かけました。特に印象に残っているのが茶山台近隣センターの南にある茶山第1公園。
この付近の緑道は、戸建住宅やテラスハウスの間を通っていますが、緑道自体が茶山第1公園と一体となって作られています。緑道脇に設置された「堺市公園緑地部」による掲示板には「公園内での禁煙にご協力お願いします」と書かれており、管理上も公園とされていることがわかります。
千里ニュータウンでは、歩行者専用道路が公園のすぐ脇を通っているところがありますが、泉北ニュータウンの茶山第1公園は、緑道自体が細長い公園というように、緑道が公園と一体となっています。


(茶山第1公園)

(堺市公園緑地部による掲示板)
千葉ニュータウンの歩行者専用道路
千葉県白井市・船橋市・印西市の千葉ニュータウンは、北総線の西白井駅から印旛日本医大駅の6駅にまたがる、南北約2~3km、東西約18kmの東西に細長い大規模ニュータウンです。まちびらきは1979年(千葉ニュータウン中央地区は1984年)と、千里ニュータウンから約20年後にまちびらきが行われています。今回歩いたのは、千葉ニュータウン中央地区だけですが、歩行者専用道路が整備されていることがわかりました。

(多々羅田公園付近)

(印西市立原山小学校付近)
千里ニュータウンのように尾根筋に歩行者専用道路、谷筋に車道を通すことによる立体交差とは異なりますが、UR原山第二団地/原山北街区公園の付近では、アーチ状のコスモスブリッジが架けられ、歩行者専用道路と車道との立体交差がなされていました。


(コスモスブリッジ)
印西市立内野小学校の北東/印西市立原山中学校の南西では、歩行者専用道路車道の下を通すかたちでの立体交差がなされていました。

(歩行者専用道路が車道の下をくぐる)
印西市立原山小学校の北東/原山幼稚園の南東は横断歩道になっていますが(平面交差)、横断歩道の部分には飛び出し防止、車の侵入防止のためにブロック状の車止めが並べて配置されています。

(横断歩道部分の車止め)
次のような光景も印象に残っています。
UR原山第二団地/原山幼稚園の東側の歩行者専用道路は、幅が広くなっており、ベンチに加えて、健康器具、ゲート状のオブジェが設置されているのを見かけました。URファーストアベニュー小倉台の南を通る歩行者専用道路にもオブジェが置かれていました。いずれも、歩行者専用道路が細長い公園のようになっていました。


(UR原山第二団地/原山幼稚園の東側)


(URファーストアベニュー小倉台)
印西市立原山小学校の東側、印西市立原山中学校の北側では、歩行者専用道路の中央に樹木があるのを見かけました。どのような理由かはわかりませんが、学校の近くであることから、子どもの安全を確保するため、自転車のスピードを落とすという効果が考えられたのかもしれません。このような光景も、千里ニュータウンでは見かけない光景で興味深いです。

(印西市立原山小学校の東側)

(印西市立原山中学校の北側)
泉北ニュータウン、千葉ニュータウンは一部のエリアを少し歩いただけの表面的な印象にすぎませんが、実際に歩くと、千里ニュータウンで導入された歩行者専用道路が、後に開発されたニュータウンでかたちを変えて継承されていることを垣間見ることができます。
■注
- 1)2023年から、「こぼれび通り」は、「URの建替え事業に合わせて無電柱化と道路整備に取り組み、安心・安全で快適な通行空間の確保及び良好な都市景観の形成」を図るための整備事業が進められている。豊中市「令和5年度(2023年度)都市基盤部事業概要」2023年5月より。
- 2)例えば、堺市が発行している「緑道ウォーキングマップ」を参照。