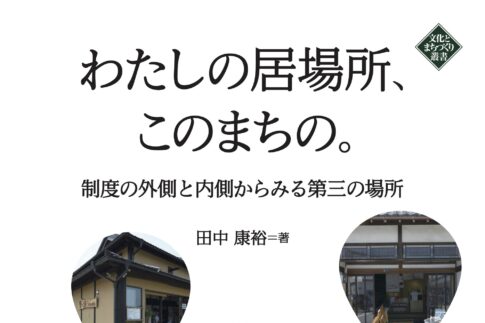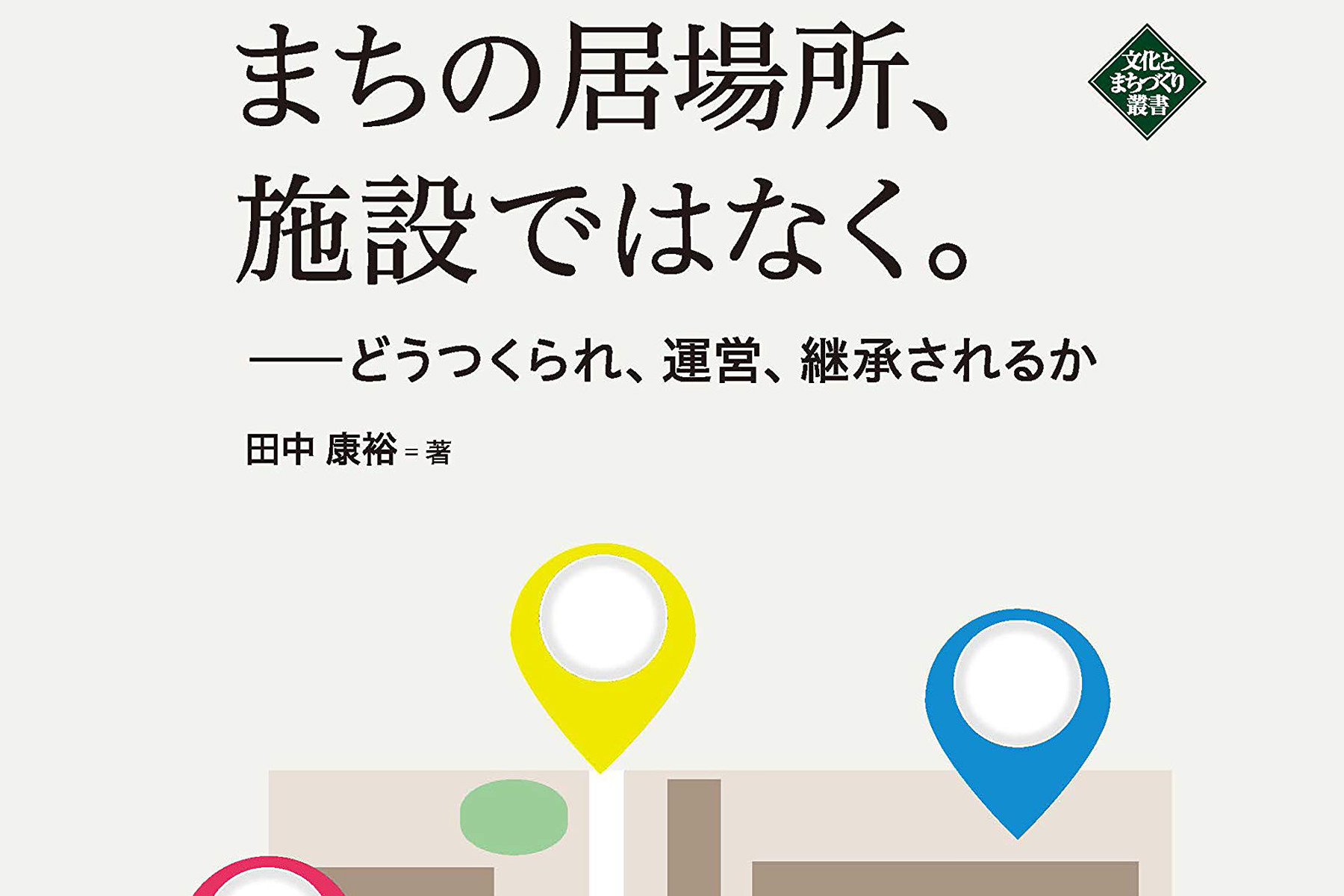2025年度の日本建築学会大会で、研究協議会「地域課題と対話し、暮らしと関係を再創造するコミュニティ拠点の最前線国際比較」が開催されました。この研究協議会の資料集に「施設でない場所における制作としての研究」という文章を寄稿しました(PDFファイルはこちらをご覧ください)。
目次
施設でない場所における制作としての研究
1.はじめに
はじめに、居場所の運営に携わってこられた方から伺った言葉を紹介したい。本稿著者が、居場所との関わりにおいて大切にしている言葉である。
「今どこに行っても、立ちあげの目的は介護予防・健康寿命延伸のためと紹介されます。結果そうであることを願いますが、・・・・・・、参加される全ての方にとって日々の生きる喜びや楽しみ、自己実現の場であり、結果、地域に生きる安心につながることを願っています。そのために必要なことをプラスしながらやっていけたらと思っています。」
現在、高齢者にとっての居場所には「介護予防・健康寿命延伸」の機能を担うことが期待されている。この方も「結果そうであることを願いますが」と話しているように、「介護予防・健康寿命延伸」を否定しているわけでないものの、何よりもまず「日々の生きる喜びや楽しみ、自己実現」の場所になることが願われている。
本稿では、既存の制度や施設に対する問題意識を背景に、既存の施設でない場所として開かれてきたコミュニティカフェ、地域の茶の間、宅老所、こども食堂などを、居場所と呼ぶ。居場所は、様々な機能を担うことで、コミュニティにおける拠点となってきたが、近年では、その機能が認知され、制度に取り込まれる制度化*1)の動きも見られるようになっている。この居場所の制度化に関わってくるのが、「日々の生きる喜びや楽しみ、自己実現」と「介護予防・健康寿命延伸」との「ずれ」である。
本稿は居場所の制度化を批判するものでないが、コミュニティ拠点を構想するうえで、居場所の制度化を振り返る作業は避けることができないと考える。そこで、本稿では居場所の制度化がどのようなプロセスかを振り返ることで、研究者はコミュニティ拠点にどのように関わり得るのかを考察する。
2.こども食堂の名付け親の決意
こども食堂の名付け親は、東京都大田区の「気まぐれ八百屋だんだん」の近藤博子さんである。2025年春、近藤博子さんがこども食堂から一線を引くことを決意した。その大きな理由は、「『こども食堂は子どもの貧困解消に役立つ、良いことだ』というイメージ」が広がりすぎていることである(杉山春, 2025)。
湯浅誠(2017)によれば、「気まぐれ八百屋だんだん」におけるこども食堂のモットーは、子どもや大人に関わらず「孤食を防ぐ」ことだが、「子どもには家庭と学校以外の居場所が少なく、特に『ここに来てもいいんだよ』と呼びかける必要がある。そこで『こども食堂』と命名」されたという経緯がある。湯浅誠は、「気まぐれ八百屋だんだん」では「こども食堂とは、子どもが一人でも安心して来られる無料または低額の食堂」と定義されていることに触れて、「『子ども』に貧困家庭という限定はついていない」ことに注意を喚起している。しかし、こども食堂は、子どもの貧困解消という機能があることに注目され、制度との関わりをもつようになっていった。湯浅誠はこの経緯を、「子どもの貧困に対する社会的注目の高まりの中で、こども食堂は、学習支援(無料塾)と並ぶ子どもの貧困対策の主要メニューとなっていく」、「社会的には、こども食堂はある意味では過度に子どもの貧困問題と結びついていった」と振り返っている。
近藤博子さんは、「大変なご家庭の子どもの支援は、行政や学校と情報共有しないと難しい」が、「行政は縦割り」で連携がいいと限らないこと、「地域の新参者」であるこども食堂は地域と関係を作りにくいことなどにも触れて、「こども食堂は行政の下請け」でないと話す(杉山春, 2025)。
「地域力、居場所作りといいますが、そんな生やさしいものではないです。そういうことを行政の方も知ってほしい。あなたたちはお仕事ですが、私たちはボランティアだということを忘れないでほしい。こども食堂は行政の下請けではありません。」(杉山春, 2025)
この発言は、ボランティア*2)を称揚することに対する問題提起として捉えることができる。中野敏男(1999)は、「ボランタリーな活動」は「国家システムにとって、コストも安上がりで実効性も高いまことに巧妙なひとつの動員のかたちでありうる」と指摘する。ただし、「ボランティア活動が機能上はシステム動員の連関の中に現にある場合でさえ、個々の場面における自発的な出会いや相互交流の喜びなどが単なる幻想にすぎないというわけではなかろう」、「ボランティア活動には、そんな社会的機能には還元し尽くせない独自な〈意味〉というものがある」。中野敏男はこのように述べたうえで、ボランティアの「当の行為者にとっての意味」と「それが現在の状況下で果たす社会的機能」を区別する必要があると指摘している。この指摘は、コミュニティ拠点をどのように構想するかにも関わってくる。
3.居場所の制度化
こども食堂をめぐる動きは、居場所の制度化として捉えることができるが、居場所の制度化が見られるのは、こども食堂だけに限らない。
居場所という言葉が頻繁に使われるようになったのは1980年代に入ってからである。萩原建次郎(2018)によれば、当時、「『居場所』と言えば、学校に行けない子どもたちのフリースペースやフリースクールをさしていた」。その後、2004年度からの「子どもの居場所づくり新プラン」による地域子ども教室、2007年度からの「放課後子どもプラン」による放課後子ども教室などを経て、「居場所の質的変容」が生じたという。地域子ども教室の活動場所は「各受託団体にゆだねられて」いたのに対し、放課後子ども教室の活動場所はできる限り小学校内で実施する方向性が打ち出されたことで、放課後子ども教室は、子どもにとって「大人と学校の教育的視線の中で再び学校空間に囲い込まれていくことを意味」するものになった。
宅老所は、「大規模施設で行われてきたケアに対する反省」から開かれるようになった、「住民一人ひとりが地域で自分らしく暮らすことを支える『小規模』で『多機能』な福祉拠点」で、1995年頃から増え始めたと言われている。2006年、「宅老所が行ってきた活動をもとに、その『地域密着』『小規模』『多機能』という形態をモデル」として、小規模多機能型居宅介護が「介護保険のなかで制度化された」(宅老所・グループホーム全国ネットワーク, 2016)。
2000年頃からコミュニティカフェ、地域の茶の間、サロンなど、従来の集会所や公民館とは異なる、気が向いたときにふらっと立ち寄れる場所が開かれてきた。このような場所には介護予防の効果があることが注目され、2015年の介護保険制度改正において、「介護予防・日常生活支援総合事業」(新しい総合事業)の中に「通いの場」として取り込まれることになった(さわやか福祉財団, 2016)。冒頭で紹介した「今どこに行っても、立ちあげの目的は介護予防・健康寿命延伸のためと紹介」されるという言葉は、こうした状況に触れたものである。
4.機能の先取り
居場所の制度化のプロセスで注目すべきは、こども食堂が子どもの貧困解消、コミュニティカフェ、地域の茶の間などが介護予防というように、居場所がもつ様々な機能の中で、ある特定の機能に注目され、その機能を担うことが期待されるというかたちで、居場所が制度の中に取り込まれていることである。
これを考える手がかりになるのが、大原一興(2005)による宅老所と高齢者施設の違いについての議論である。大原一興は、多くの宅老所が「最初は小規模な民間のデイサービスから始まり」、次第に宿泊や居住ができるようになるという展開をみせていること、「対象者も高齢者はきっかけに過ぎず」、「障害を持つ人のための居住の場、小さな子の預かり、引きこもり中学生の日中過ごす場」というように「制度に乗らない新たなサービスをむしろ創出することになっている」ことに触れて、「宅老所活動の存在意義は、提供されるサービス機能ではなく、地域の要求を引き出すための装置として有効となる点にある」と指摘する。その一方で、「高齢者施設では、機能が単独で先行し施設が建設され、しかるのちにそれに適した居住者(例えば要介護度の高い人、認知症の人など)が入居者として募集される」。ここでは「機能が要求よりも先行」しており、「先に要求がありそれに対して機能が発生する、という本来の『要求-機能』関係が倒立している」*3)。大原一興は、このように居場所と施設の違いを「要求-機能」関係の違いとして捉えている。
居場所の制度化においては、子どもの貧困解消、介護予防などのように、ある特定の機能への注目があった。しかし、居場所においてこれらは、生じてくる具体的な要求への対応として、結果として備わる機能の1つだったはずである。これより、居場所の制度化とは、具体的な要求に先立って、機能を抽出することから始まると捉えることができる。そして、イバン・イリイチ(1984)が、「専門家の特徴」は「人を顧客と定義し、その人の必要を決定し、その人に処方を申し渡せる権威」にあると指摘するように、機能を抽出するプロセスには、研究者を含めた専門家が関与している*4)。
5.抽象的な利用者
社会福祉学者の三浦文夫(1987)は、「社会福祉における『実践』レベルと『政策』レベル」における「ニード」について次のような議論を行っている。実践レベルでは「具体的な要援護者」が対象であり、「その者にとっての『自立』なり『社会的統合』は何かということとの関連において、『ニード』の解決とかその取組みが問題とされていく」。それに対して、政策レベルでは「あらかじめ措定されている政策目的に沿って個々のニードを範疇化あるいは集合化して、政策ニードとする」ことが行われる。
本稿の冒頭で取りあげた「日々の生きる喜びや楽しみ、自己実現の場」と「介護予防・健康寿命延伸」との「ずれ」、あるいは、中野敏男(1999)が指摘するボランティアの「当の行為者にとっての意味」と「それが現在の状況下で果たす社会的機能」の違いもここにあると考えることができる。
居場所の機能は「個々のニード」への対応の結果として備わってくる。それに対して、制度や施設における機能は先取りして抽出されるものだったが、これは、「あらかじめ措定されている政策目的に沿って」、つまり、専門家によって認識された社会課題を解決するという目的に沿うかたちで「個々のニードを範疇化あるいは集合化」することになっている。つまり、子どもの貧困解消、介護予防などの機能が抽出されたとすれば、その背景には、これらが社会課題だという専門家の認識がある。
伊藤俊介(2007)は「集合住宅や公共施設は不特定多数を対象とすることから、実際の利用者ではなく抽象的な利用者像を前提に計画」せざるを得ないと指摘する。この指摘から、制度や施設においては、何らかの社会課題を解決しようとする専門家の目的に沿うかたちでの「政策ニード」をもつ「抽象的な利用者」が仮構されていると捉えることができる*5)。
ここから次のような「要求-機能」関係の反転が生じる。橘弘志(2019)は、施設の環境やサービスは「あくまでも運営者・計画者によって定められたもの」であるため、「私たちが『ニーズ』として捉えているものは、今や私たちが生身の身体として環境と関わる中で見出されるものでもなければ、他者との生き生きとした関わりの中で立ち現れるものでもない。あくまで個人としての要求でありながら、実は外部から喚起させられたものに他ならない」と指摘する。制度や施設が生み出されると、人々は「政策ニード」を、元々自らがもっていたかのように認識してしまうというように、抽出された機能が、逆に人々の要求を規定していくのである*6)。
6.コミュニティ拠点における研究
居場所の制度化がどのようなプロセスかを踏まえることで、研究者のコミュニティ拠点との関わりとして2つの可能性を考えることができる。
新たな施設として
1つは、機能を抽出すること、その機能をどのように実現し得るかを考察することで、コミュニティ拠点を新たな施設として構想することである。これは、研究者がこれまで担ってきた役割とも言えるが、今後も、この役割がなくなるわけではない。
大原一興(2005)が宅老所と高齢者施設の違いの議論で問題視していたことは、高齢者居住施設の供給施策が一機能一殿舎型になっていること、つまり、「『サービスを受ける場』と『生活拠点』とが一対一の対応関係」になっていることで「身体状況など居住者のサービスとニーズが一時変わると住まいも移らなくてはならない」というように、高齢者が「リロケーション(生活拠点移動)」を余儀なくされるからである。コミュニティ拠点は一機能一殿舎型の施設整備のあり方を乗り越えるものであり、危惧されている「リロケーション(生活拠点移動)」は発生しないとも言える。
社会課題を解決するための子どもの貧困解消、介護予防などの機能が重要であることは言うまでもないが、問題なのは、近藤博子さんが「こども食堂は行政の下請けではありません」と話していたように、これらの機能をボランティアが担うのを期待し、制度に取り込もうとすることである。繰り返しになるが、ボランティアにより運営される場所が、具体的な要求への対応の結果としてこれらの機能を担うことはあり得るとしても、それは、これらの機能を先取りして抽出することとは異なる。コミュニティ拠点を施設として構想するうえでは、研究者がボランティアに依存しないことが求められる。
施設でない場所として
もう1つは、コミュニティ拠点を施設でない場所として捉えるもので、特にボランティアで運営される場所において重要になる。近藤博子さんは、「ボランティアとしての範囲」でできることとして、次のように話している。
「お隣さん同士がもう少し気を遣いあって、地域を作るほうが大事だと思います。多く作りすぎた煮物や頂き物の野菜を届けるとか。少しの間子どもを預かるとか。それが、ボランティアとしての範囲でできる地域力だと思います。」(杉山春, 2025)
本稿著者は、これに共通する話を何度か伺ったことがある。東京都江戸川区で「親と子の談話室・とぽす」*7)を運営する白根良子さんは次のように話す。
「今日来たお客さまには、精一杯、ここに来たらゆったりしてもらえるっていう、それがやっぱり目標ですね。あまり大きなことっていうのはないですね。なぜか、『あぁ、ここに来てほっとしたわ』、『今晩何にする?』なんて言って、『今晩何だか決まってないわ』なんてしゃべりながらでも、夕食をつくる元気が出るんですね。・・・・・・。そんな、やっぱり小さいところにあるような気がする。」
新潟市で「実家の茶の間・紫竹」*8)の運営に携わる河田珪子さんは次のように話す。
「来られる一人ひとりが楽しんでる、ここへ来てよかったって。そういう眼差しで、みんなが自分と一緒じゃないけど、みんなが『ここへ来てよかったね、ここがあってよかったね』って思っていてくださるっていうことを、いつも、いつも確かめながらやってるだけなんですよね。それ以上でも以下でもない。」
目の前の人の要求に対応することは容易ではない。しかし、目の前にいる人と過ごす時間は豊かなものにもなり得る。その時間は、他の何らかの目的を実現するための手段ではなく、それ自体が尊いものであり、「それ以上でも以下でもない」*9)。研究者の目には、その結果として、子どもの貧困解消、介護予防などの機能が実現されているように映るかもしれない。それゆえ、これらの機能を「それ以上」のものとして抽出したくなるかもしれない。しかし、それが居場所の制度化の始まりだとすれば、目の前にいる人との時間をいかに豊かなものにできるのかに焦点を当てた研究の可能性があると考える。
東浩紀(2023)は、ハンナ・アーレントが「人間が『活動的な生』を送るうえでの営為」を労働(labor)、制作(work)、活動(action)の3つに分類していることに触れて、次のような議論を行なっている。ハンナ・アーレントは公共性を「開放性と持続性によって定義した。開放性としての公共性は活動によって可能になり、持続性としての公共性は制作によって可能になる」、「政治家や哲学者は確かに公共性を担う。・・・・・・。しかしその営みはそれだけでは消えてしまう。それが歴史になるためには、本が書かれ、記念碑が建てられ、ものづくりが行われなければならない。本当の公共性は、活動と制作が組み合わされなければ実現しないのである」。
目の前にいる人との時間は「それだけでは消えてしまう」。それゆえ、研究者は、まずは言葉を使う専門家として制作に携わることで、「持続性としての公共性」を可能にするという重要な役割も担い得る。
■注
- 1)五十嵐太郎(2002)が、「日本語では別々の単語だが、英語の『インスティテューション』という言葉は『制度』と『施設』の両方の意味をもつ。ある施設が成立するということは、それを支える制度が確立しているということだ。福祉施設というように、制度が機能している状況を含めて、はじめて施設という言葉は生きている。一ヶ所しか存在しえない特殊な建物は施設と呼ばない」と指摘するように、制度と施設は不可分のものである。
- 2)ボランティアは無報酬という意味で捉えられることもあるが、本稿でいうボランティアとは、自発的にという意味である。
- 3)大原一興の議論は、佐々木嘉彦(1975)の「『人-物』関係は、人間の行為において、『人の要求』と『物の機能』を媒介して人と物が結びつく関係としてとらえることができる」という議論を踏まえたものである。
- 4)本稿著者は、建築計画学における「まちの居場所」を対象とする事例研究が、「要求-機能」関係を反転させて捉えることで、「まちの居場所」の制度化に寄与する可能性があることを議論した(田中康裕, 2021a)。
- 5)中野敏男(1999)は、「『ボランティアという生き方』の称揚とは、このように抽象的な『ボランティア主体』への動員のことなのであり、この主体=自発性は、抽象的であるがゆえにかえって、『公益性』をリードする支配的な言説状況に・・・・・・どうしても親和的にならざるをえない仕掛けになっている」と指摘する。
- 6)山本哲士(1979)は、イバン・イリイチの議論をふまえ、これを「制象化」という用語で議論している。「教育や運ぶことや治療が〈必要〉となったとき、学習や自分の移動や自分の治癒・健康といった『使用価値』は他律的な働きかけの結果となっている。これが『制象化』のレベルである。そして、他律的な様式は商品としての価値に転化している。・・・・・・。この『価値』は、制度の過程をとおしてうみだされるのであるが、『使用価値』が転化した結果をそうのべているのである。・・・・・・。自律的な使用価値が諸価値に制象化されているから制度化がなされるのである」。
- 7)「親と子の談話室・とぽす」については、田中康裕(2021b)などを参照。
- 8)「実家の茶の間・紫竹」については、田中康裕(2021b, 2025)などを参照。
- 9)「それ以上でも以下でもない」というのは、國分功一郎(2025)が指摘する「目的-手段連関」から自由になることとして捉えることができる。
■参考文献・資料
- 東浩紀(2023)『訂正可能性の哲学』ゲンロン
- 五十嵐太郎(2002)「ビルディングタイプとはどういうものか」・五十嵐太郎 大川信行『ビルディングタイプの解剖学』王国社
- 伊藤俊介(2007)「建築地理学の考え方」・長澤泰 伊藤俊介 岡本和彦『建築地理学:新しい建築計画の試み』東京大学出版会
- イリイチ、イバン(1984)「専門家時代の幻想」・イリイチ、イバン他(尾崎浩訳)『専門家時代の幻想』新評論
- 大原一興(2005)「施設と地域の再構築」・『建築雑誌』Vol.120, No.1533, pp.20-21
- 國分功一郎(2025)『手段からの解放』新潮新書
- 佐々木嘉彦(1975)「生活科学について」・日本生活学会編『生活学 第一冊』ドメス出版
- さわやか福祉財団編(2016)『居場所・サロンづくり』全国社会福祉協議会
- 杉山春(2025)「「こども食堂から一線を引く」 《こども食堂》の名付け親が決意した背景 ボランティアでできる支援には限界がある」・『東京経済オンライン』2025年5月30日
- 宅老所・グループホーム全国ネットワーク編(2016)『宅老所』全国社会福祉協議会
- 橘弘志(2019)「「まちの居場所」の背景と意味」・日本建築学会編『まちの居場所:ささえる/まもる/そだてる/つなぐ』鹿島出版会
- 田中康裕(2021a)「居場所の制度化と建築計画学における事例研究」・『日本建築学会計画系論文集』Vol.86, No.790, pp.2609-2620
- 田中康裕(2021b)『わたしの居場所、このまちの。:制度の外側と内側から見る第三の場所』水曜社
- 田中康裕(2025)「地域における助け合いの拠点「実家の茶の間・紫竹」が実現してきたこと」・『さぁ、やろう』さわやか福祉財団, 第26号, pp.30-37
- 中野敏男(1999)「ボランティア動員型市民社会論の陥穽」・『現代思想』Vol.27-5, pp.72-93
- 萩原建次郎(2018)『居場所:生の回復と充溢のトポス』春風社
- 三浦文夫(1987)『増補社会福祉政策研究:社会福祉経営論ノート』全国社会福祉協議会
- 山本哲士(1979)『学校・医療・交通の神話:イバン・イリイチの現代産業社会批判』新評論
- 湯浅誠(2017)『「なんとかする」子どもの貧困』角川新書