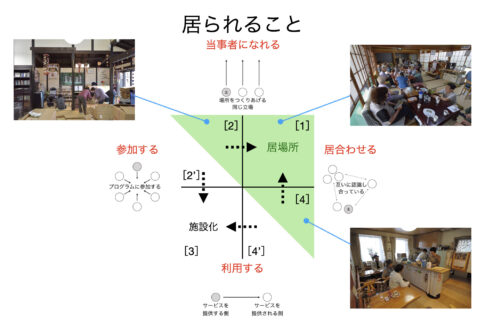先日、下の写真に映っている女性の行動はどのように記述できるかという議論をする機会がありました。「たたずむ」と記述するか、あるいは、「塔を見る」と記述するか、「ビニル袋を手に下げる」と記述するか。

ある方から、観察者がどう感じるかだけでなく、まずこの女性がどのように思っているかを捉えることが大事ではないかという意見がありました。この意見をきっかけとして、次のような話をしました(内容の再構成、補足を行っています)。
他者の姿がまず目に飛び込んでくること
居方:他者が居ることの意味を扱う概念
住宅のように特定の人のための場所と違って、不特定多数の人々がいるパブリックな場所では、個々人の思いを捉えることは困難です。しかし、これは諦めということでなく、たとえ個々人の思いがわからないとしても、他者が居るのを見るという体験自体に意味があるのではないか。
建築学者の鈴木毅(2004)による「人間がある場所に居る様子や人の居る風景を扱う枠組み」としての「居方」*1)は、まさにこの視点から場所の価値を捉えようとする概念。鈴木毅は他者が居ることの意味を次のように指摘しています。
「様々な居方を検討して分かってきたことは、他人がそこに居ることの意味である。・・・・・・、ある場所に人が居るだけで、その人と直接のコンタクトがなくても、彼を見守っている者には様々な情報・認識の枠組みが提供されるのである。中でも重要なことは、ある人は、(自分自身では直接みえない)自分がその場に居る様子を、たまたま隣りにいる他者の居方から教えてもらっているという点である。つまり、他者と環境の関係は、観察者自身の環境認識の重要な材料を提供しているのである(図5-1)。言ってみれば、『あなたがそこにそう居ることは、私にとっても意味があり、あなたの環境は、私にとっての環境の一部でもある』ということになる。」(鈴木毅, 2004)
パブリックな場所を訪れた時、他者の姿が目に飛び込んでくることがあります。この体験がもつ可能性に注目した場所として、新潟市の「実家の茶の間・紫竹」をあげることができます。
「実家の茶の間・紫竹」
「実家の茶の間・紫竹」は、新潟市最初の「地域包括ケア推進モデルハウス」(基幹型地域包括ケア推進モデルハウス)として開かれた場所で、「大勢の中で、何もしなくても、一人でいても孤独感を味わうことがない“場”(究極の居心地の場)」(河田珪子, 2016)を実現することが目指されています*2)。

(空き家を改修して開かれている)

(茶の間の戸)

(茶の間で思い思いに過ごす人々)
「実家の茶の間・紫竹」の河田珪子さんが次のように話されているように、茶の間の戸を開けて入ることは、訪れる人にとって心理的なバリアになる。だから、入って来る人に視線が集中しないようなテーブル配置とすること、そして、初めて訪れる人には「できるだけ外回り」に座ってもらい、思い思いに過ごしている人々の姿を見てもらうことで、「色んな人がいていいんだっていうメッセージ」を伝えることが考えられています。
「ここの笑い声とか話し声とか、外に漏れ漏れですね。楽しげですね。その時、戸を開けた時、みんなが『何、あの人何しに来たの?』『誰、あの人?』とかって怪訝な目がぱっと向いたら、それだけで入れなくなったりする。だから、ここでは入口で、来てくださった方をどこに座ってもらうかまで考えて座ってる。初めて来た人は、できるだけ外回りに座ってもらおう。そうすると、あんなことも、こんなこともしてる姿が見えてきますね。すると、色んな人がいていいんだっていうメッセージが、もうそこへ飛んでいってるわけですね。そっから始まっていくんです。」
このようにして「実家の茶の間・紫竹」に迎えられた人は、今度は迎える側の人となり、新たに訪れる人に対して「その人が居てもいいよというメッセージ」を伝えていく。
「今度、迎える側は全ての人が、その人が居てもいいよというメッセージを出していくという。表情とか振る舞いで。みんな、どの人が来ても『よう来たね、ここにゆっくりしてね、居てもいいんですよ、好きなように過ごしてね』っていうメッセージを、みんなして出していく。」
「実家の茶の間・紫竹」は、このようなかたちで他者の姿が目に飛び込んでくるという体験がもつ可能性に注目して、人々を迎えることが考えられています。これと同じようなことが書かれた文章を最近読みました。イタリアのボローニャ市立中央図書館「サラボルサ」について書かれた文章です。
ボローニャ市立中央図書館「サラボルサ」
ボローニャ市立中央図書館「サラボルサ」(以下、「サラボルサ図書館」)は、ボローニャ中心部のマッジョーレ広場に面した建物に、2001年にオープン。建物は、元々は証券取引所で、「サラボルサ」というイタリア語は、証券取引所を意味しています*3)。
「サラボルサ図書館」に入ると、3層吹き抜けのアトリウムが目に飛び込んできます。アトリウムに面して、1階には司書のいるカウンター、乳幼児のためのスペース、カフェなど、2階には雑誌の閲覧スペース、学習スペースなどがあります。3階は市、ボローニャ大学、銀行、関連企業等で構成される委員会が運営するアーバン・センターとなっており、都市計画・事業の展示、会議室などがあります。地下には講堂のほか、ローマ時代の遺跡があります。

(広場に面した「サラボルサ図書館」)
図書館計画のアドバイザーとして「サラボルサ図書館」にも携わったアントネッラ・アンニョリは、図書館を「屋根のある広場」と表現しています。
「将来の図書館は、世界中どこであろうと、“屋根のある広場”、つまりこれまで示してきた広場の特徴のうちの、少なくともいくつかは持ち合わせた場所になる以外に生き残る道はない。・・・・・・。容易にそれと分かる建物であり、一日のうちでさまざまに表情を変え、豊かな体験を提供する場であるべきだろう。安全性と快適さを保証するだけではなく、いろいろなものに出会うことができ、だからこそこれといった理由がなくともやって来るような、そんな場所にする必要がある。」(アントネッラ・アンニョリ, 2011)
ここで指摘されている「これまで示してきた広場の特徴」として、次の6つがあげられています。
- ①広さ:「市民が集まりやすい場にするには、広すぎてはいけない」
- ②レジビリティ(分かりやすさ):「都市の部分とその一貫した組織構造を人が認識できること」
- ③多様性:「共生の場は多彩な機能を提供しなければならないし、つねに発見のある場であらねばならない」
- ④安全性
- ④快適さ:「腰を下ろす場所があるか、そして、日陰があるか」など
- ⑤出会いの場
実際に「サラボルサ図書館」を訪れて、アトリウムで堂々と携帯電話で話をしている人がいたこと、走り回って遊ぶ子どもがいたこと、1階のカフェからはカチャカチャという食器がふれる音が聞こえてきたことが特に印象に残っています。
「サラボルサ図書館」は、「屋根のある広場」という表現の通り、広場の一画に本や新聞が置かれたコーナーがもうけられており、本を読んだり、勉強をしたりしている人もいる。もちろん、パブリックな広場として、飲食している人、携帯電話で話をしている人もいれば、遊んでいる子どもたちもいる。飲食禁止で、静かに過ごすことが求められる従来の図書館のイメージを覆す場所で、カチャカチャという食器がふれる音さえも、ここがパブリックな場所であることを現すようで心地良く響きました。


(3層吹き抜けのアトリウム)
「サラボルサ図書館」、特に、アトリウムについて、建築学者の小篠隆生と小松尚は次のように指摘しています。
「『本が迫ってこない』というペルティーニの雰囲気を生み出す空間構成や活動プログラムは、『屋根のある広場』と呼ぶにふさわしい公共図書館の特徴のひとつと言えそうである。まず、建物に入ると吹き抜け空間が迎えるという視認性が高く一体感のある空間構成は、規模は違うがサラボルサではアトリウムが迎える構成と共通点が多い。入りやすくて視認性が高く、そこで思い思いに過ごしている市民の姿が見える空間が、まず来館者を迎える。迎えるのは本の集積ではなく、まさに『本が迫ってこない』空間である。またそれは、本の貸し借りや読書、勉強に留まらない、公共図書館の今日的な役割を空間的にも機能的にも体現していると言っていいだろう。」(小篠隆生・小松尚, 2018)
「また、この延長線上には、サラボルサでたたずむ来館者の姿や市民活動の様子までもが、図書館で個然で無意識のうちに得られる『暗黙知』の情報になり得るという見方が成り立つのではないか。」(小篠隆生・小松尚, 2018)
ここで指摘されていることも、他者の姿が目に飛び込んでくるという体験がもつ可能性に言及するものだと言えます。「サラボルサでたたずむ来館者」一人ひとりの思いはわからないかもしれない。けれども、来館者がそこにたたずんでいること自体が、私にとって意味をもたらすということになります。
個々人の思いは捉えることができないかもしれない。このことは、同時に、自分自身の思いは周りの人々には理解されないことを意味します。そうであっても、人が居ること自体が、既に他者に影響を与えてしまっている。パブリックな場所において、人は否が応でもパブリックな存在になってしまうということだと思います。
「サラボルサ図書館」を初めて訪れた日、悪天候のため臨時休館となっていました。臨時休館だったことを知らずに「サラボルサ図書館」に行ったわけですが、同じように臨時休館であることを知らずに「サラボルサ図書館」に訪れている人を何人も見かけました。小さな子どもを連れた母親、大学生ぐらいの若者、そして、高齢の人。みな、「サラボルサ図書館」の入口に貼られた小さな掲示を見て、(この記事で書いたように他者の思いは捉えることができないわけですが、残念そうに)帰って行くのを見かけました。
偶然見かけたこのような光景からも、「サラボルサ図書館」が多くの人々にとって大切な場所になっていることが伝わってきました。


(臨時休館の貼り紙を読む人)
この日の夕方は、マッジョーレ広場に面したサン・ペトローニオ大聖堂でセレモニーが行われており、聖堂から出発した行進が「サラボルサ図書館」の前を通り過ぎて行くのを見かけました。

(「サラボルサ図書館」の前を通るパレード)
■注
- 1)「居方」については、こちらの記事を参照。
- 2)「実家の茶の間・紫竹」は、こちらの記事、および、河田珪子(2016)、田中康裕(2021)などを参照。
- 3)「サラボルサ図書館」については、小篠隆生・小松尚(2018)、アントネッラ・アンニョリ(2011)などを参照。
■参考文献
- アントネッラ・アンニョリ(萱野有美訳)(2011)『知の広場:図書館と自由』みすず書房
- 小篠隆生・小松尚(2018)『「地区の家」と「屋根のある広場」:イタリア発・公共建築のつくりかた』鹿島出版会
- 河田珪子(2016)『河田方式「地域の茶の間」ガイドブック』博進堂
- 鈴木毅(2004)「体験される環境の質の豊かさを扱う方法論」・舟橋國男編『建築計画読本』大阪大学出版会
- 田中康裕(2021)『わたしの居場所、このまちの。:制度の外側と内側から見る第三の場所』水曜社